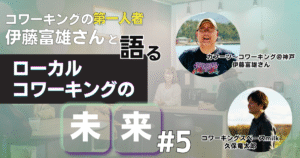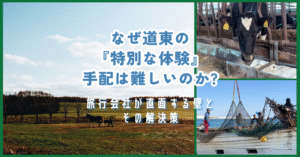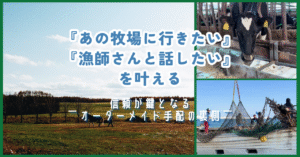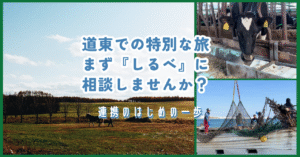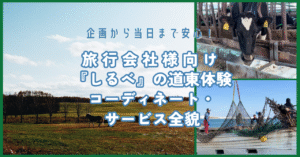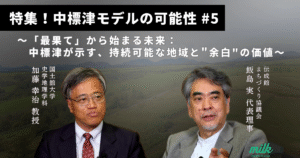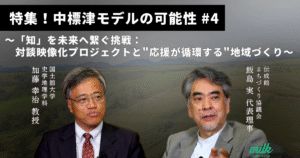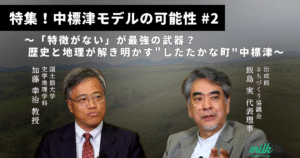はじめに:グランプリ受賞のご報告と、この記事でお伝えしたいこと
この度、私たち株式会社しるべが地域側コーディネーターとして深く関わらせていただいたNFTプロジェクト「最果ていきもの学校 漁師編」が 観光庁主催の「観光×NFTアワード2024(Japan Tourism NFT Awards)」にて、体験価値・フィジタル部門のグランプリ(最優秀賞)を受賞いたしました!
本プロジェクトは、北海道標津町の若手漁師グループ「波心会(はしんかい)」、KDDI株式会社、株式会社SAGOJOとの連携により実現したものです。この記事では、「最果ていきもの学校 漁師編」が「どんな企画だったのか?」「なぜNFTという形をとったのか?」そして「どんな成果と学びがあったのか?」を具体的にお伝えし、この仕組みにご興味を持たれた皆様へのご案内もさせていただきます。
【課題】「もっと知りたい」のに近づけない… 地域と外部の静かな壁
「スーパーに並ぶ魚の向こう側に、どんな物語があるんだろう?」
「漁師さんのリアルな仕事や想いをもっと深く知りたい」
近年「地域の一次産業やそこに生きる人々の”本物”に触れたい、深く関わりたい」というニーズが高まっています。しかし現実には、漁業のような一次産業の現場は安全管理や資源保護、そして何より日々の生活への配慮から、外部の人を安易に受け入れることが難しい状況があります。
結果として「特別な縁」がなければ現場を見ることも、そこへ足を踏み入れることさえできない、見えない壁が存在していました。
一方で地域側、例えば標津町の漁師グループ「波心会」の皆さんも「自分たちの仕事の価値や海への真剣な想いを、本当に理解してくれる人に伝えたい」という熱い気持ちを持っています。
魚を単なる”資源”ではなく”いのち”として扱い、未利用魚の活用や神経締めといった技術でその価値を最大限に引き出そうと挑戦する彼らの姿は、国内外で高く評価され、ドキュメンタリー映画『ときと』にもなっています。
この両者の「もっと知りたい」「もっと伝えたい」という想いを、どうすれば繋ぐことができるのか?
それが私たちの課題意識でした。
【挑戦】NFTで“特別な縁”をデザインする:「最果ていきもの学校 漁師編」の全貌
そこで私たちが挑戦したのが、NFT技術を活用した「最果ていきもの学校 漁師編」です。
これは単なる体験ツアーではありません。参加の証としてNFTを購入し段階的に学びを深め、最終的にリアルな現場との繋がりを得る、まったく新しい形の「学校」でした。



- NFT=「最果てデジタル学生証」:
参加者はまず入学の証として、オリジナルデザインのNFT(デジタル学生証)を購入します。価格帯によって特典が異なる複数の種類を用意しました。(販売総数30個は、1ヶ月足らずでほぼ完売) - オンライン講座で学ぶ(全3回):
NFT保有者は波心会の漁師さんたちが講師を務めるZoomでのオンライン講座に参加。私たちが現場から中継し、リアルタイムで質疑応答も行いました。
1回目: 波心会の取り組み紹介、海との向き合い方
2回目: 未利用魚(カジカ、カレイ等)の価値と活用法(捌き方、商品化例を実演)
3回目: 魚の価値を高める神経締め・仕立ての技術 - 五感で学ぶ「未利用魚BOX」:
オンライン講座の後、学んだばかりの未利用魚や神経締めの有無で比較できる魚などの詰め合わせが自宅に届きます。講義で学んだレシピを参考に調理し、舌でその違いを体験。
「知る」だけでなく「わかる」学びを提供しました。(参考:波心会のクラファン商品 ※参考資料③) - リアルな現場へ「漁業体験」(高額NFT特典/抽選):
最も深く学びたい方向けでは実際に標津町を訪れ、漁船に同乗して漁(しまえび漁など)に同行できる特別な体験を用意しました。
【そもそも解説】NFTって何? なぜ「デジタル学生証」に?
NFTとは「Non-Fungible Token(非代替性トークン)」の略で、簡単に言えば「偽造不可なデジタル証明書」です。
これを持つことで、あなたがそのデジタルデータ(今回は学生証アート)の唯一の所有者であることが証明されます。
今回、単なる参加権ではなく「デジタル学生証」としてNFTを活用したのは、参加者に「学校の一員」としての所属意識と学び続けることへの動機付け、そして「特別な体験へのアクセス権」としての価値を持たしたかったからです。
【核心①】なぜNFT? “手間”が「熱意の証明」になる仕組み
正直に言うと、NFTという新しい技術を導入することに当初、地域側(特に漁師さん)に戸惑いもありました。
「なぜ、そんな面倒なことを?」と。
しかし私たちがNFTにあえてこだわったのには理由があります。それはNFTを購入し、設定して講座に参加するという一連の「手間」が、参加者の「本気度=熱意」を測るフィルターとして機能すると考えたからです。
誰でも簡単に参加できるツアーでは、どうしても受け身の姿勢になりがちです。
しかしNFTというハードルを越えて参加してくれた方は「そこまでしてでも、波心会の活動を知りたい、関わりたい」という強い想いを持っているはず。
その熱意は受け入れる地域側にとって「この人なら信頼できる」「安心して深く関われる」という大きな安心感に繋がります。
実際、プロジェクト途中で調整が難航し、中止になりかけた時もありました。
しかし最終的に漁師さんたちがGOサインを出してくれたのは「この企画は、しるべが熱意のある人を選んで連れてくるためのもの。しるべが責任を持つなら」という、私たちとの日頃からの信頼関係と企画の趣旨への理解があったからでした。
結果として、NFTは地域と外部の人が出会う上での心理的なハードルをポジティブな形で機能させる装置となったのです。
【核心②】“学び尽くしたくなる”引力:NFTが促す能動的な関わり
もう一つ、NFTがもたらした効果は参加者の「能動的な学び」を促したことです。
「せっかくNFTを買ったのだから、しっかり学んで元を取りたい」「このデジタル学生証の価値を高めたい」そんな心理が自然と働きます。
そしてオンライン講座では熱心に聞き、送られてきた魚は自ら調べながら捌き、味や地域の食文化について、より探求する。
参加者からは「普段スーパーで何気なく見ていた魚の産地を気にするようになった」「この企画がきっかけで中標津が好きになり、ついには会社を設立してしまった」といった嬉しい声も聞かれました。
これはまさに波心会の漁師さんたちが望んでいた「受け身ではなく、深く理解しようとしてくれる」参加者の姿そのものでした。
NFTという仕組みが、図らずも提供する側とされる側の理想的な関係性を築く一助となったのです。
【舞台裏】地域と大手をつなぐ「しるべ」の役割:信頼の翻訳と場の提供
このプロジェクトの成功には、KDDI(地方創生部門、αUプラットフォーム提供)やSAGOJO(企画・実働)といった外部パートナーとの連携も不可欠でした。
しかし大手企業の論理やスピード感と地域の文化や価値観との間には、時としてギャップが生まれます。NFTという新しい技術に対する理解度も異なります。
その間に入り、双方の言葉を「翻訳」し、利害を調整してプロジェクトを円滑に進める。
それが私たち「しるべ」と、その拠点であるコワーキングスペース「Milk」が果たした役割でした。
特にNFT販売のためのクリエイティブ(見せ方)と漁師さんの哲学との間の調整は最も苦労した点です(笑)
日頃からの信頼関係がなければ、乗り越えられなかったかもしれません。
今後、地域と外部企業・人材が連携するプロジェクトはますます増えていくでしょう。
その中で私たちのような、地域のリアルを理解し、外部の論理も解釈できる「地域内翻訳者」「ローカルハブ」の存在価値は、さらに高まっていくと確信しています。
【成果とこれから】アワード受賞の意義と、地域連携の新しい可能性
観光×NFTアワード2024でのグランプリ受賞は、この取り組みが「新しい観光体験の価値」と「デジタルとリアルの効果的な融合(フィジタル)」を実現した点が高く評価された結果だと受け止めています。
参考資料

今回の挑戦から得られた最大の学びは「関係性のデザイン」の重要性です。
NFTはあくまでツールの一つですが「参加のハードルを設けることで熱量を可視化する」「段階的な学びと体験を提供する」「継続的な関わりを促す」といった考え方はNFTを使わずとも、様々な地域連携プロジェクトに応用できるはずです。
成功の鍵は①地域の本質的な価値を深く理解すること、そして②地域の内外を繋ぐ信頼できる「ハブ(調整役)」が存在することだと考えます。
【ご案内】この取り組み、視察しませんか?
「自分たちの地域でも、こんな風に外部と連携できないだろうか?」
「地域資源を活用した新しい体験プログラムを作りたいが、どう進めればいいかわからない」
もし、そのようにお考えの自治体関係者、企業担当者、地域おこし協力隊、あるいは熱意ある個人の皆様がいらっしゃいましたら、ぜひ一度 中標津を訪れてみませんか?
NFTはあくまで入口の一つ。
私たちはこれからも地域と外部をつなぎ、継続的で深い関係性を築くための挑戦を続けていきます。
ご興味のある方はしるべにお気軽にお問い合わせください。
参考サイト・関連記事




北海道中標津町を拠点に「最果てを、最先端に」をビジョンとして活動。
コワーキングスペース運営を軸に旅行サービス手配業、まちづくり事業など、地域をフィールドとした様々な実験・プロジェクトを展開しています。