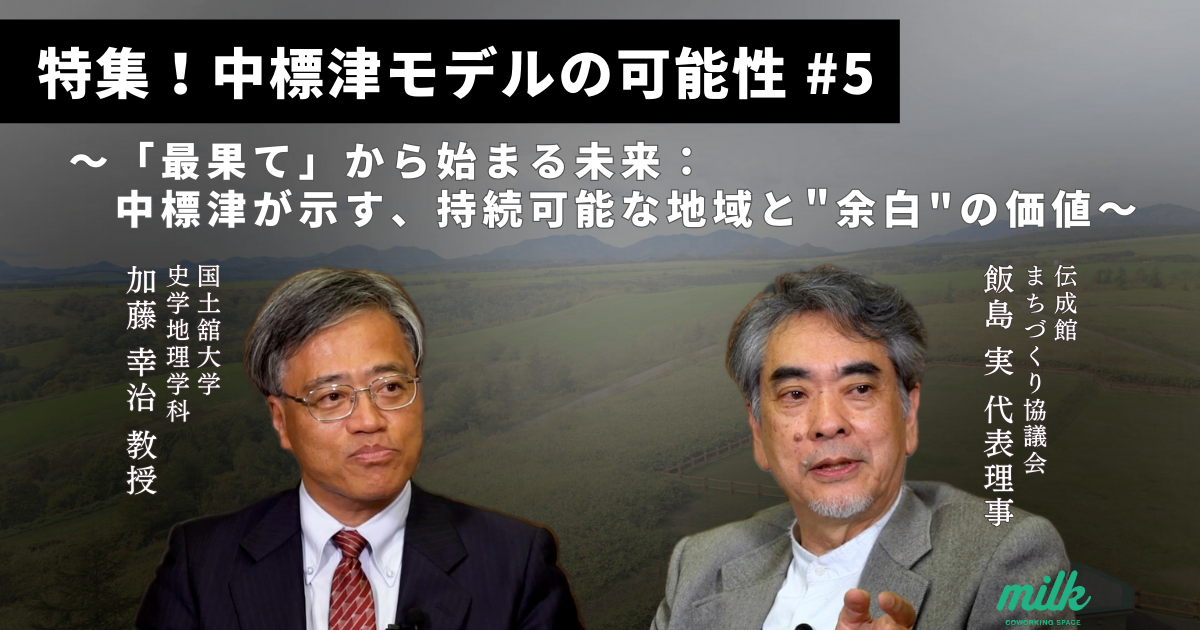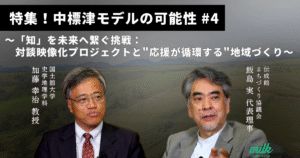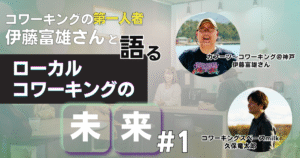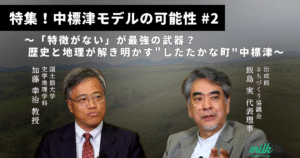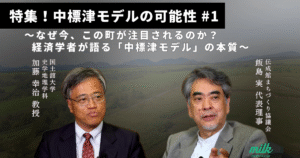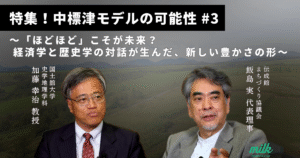経済学的な合理性から見出されたコンパクトな都市構造。 ~特集#1~
歴史と地理が育んだ「特徴のなさ」という名の独自性。 ~特集#2~
異なる視点の対話から浮かび上がった「ほどほど」という新しい豊かさの指標。 ~特集#3~
そして、その貴重な「知」を未来へ繋ごうとする地域の挑戦。 ~特集#4~
4回にわたって探求してきた特集「中標津モデルの可能性」。
国士舘大学の加藤浩嗣教授とNPO法人伝成館の飯島実理事長による異色の対談は、北海道東部の小さな町・中標津がこれからの日本の地域づくりにおいて、いかに示唆に富んだ存在であるかを浮き彫りにしてきました。
最終回となる本稿では、この対談全体から得られた学びを総括し、中標津、ひいては日本の地方がこれから描くべき未来像について、改めて展望します。
キーワードは「ハブ機能」「広域連携」、そして「余白」です。
未来への視点①:地域と世界を繋ぐ「ハブ」としての可能性
対談の中で加藤教授、飯島氏ともに繰り返し言及したのが、中標津が歴史的・地理的に担ってきた周辺地域への「中心性」=「ハブ」としての役割でした。
商業施設や病院、空港といった物理的なインフラだけでなく、情報や人が集まり、交流する結節点としての機能です。
今後、この「ハブ機能」は、地域の持続可能性にとってますます重要になるでしょう。
コワーキングスペースmilk(本対談の主催者)のような場が地域内外の人々、多様な専門性やスキル、そして新しいアイデアを繋ぎ合わせる触媒となる。
そうすることで地域の中から新しいビジネスやプロジェクトが生まれ、関係人口が育まれ、地域経済が活性化していく…そんな好循環を生み出すエンジンとしての役割が期待されます。
これからの地域に必要なのは単に人を呼び込むだけでなく、地域内外の多様な主体(住民、企業、NPO、行政、移住者、関係人口…)が対等な立場で連携し、共に価値を創造していく「共創」のプラットフォームです。
中標津が持つ「ハブ」としてのポテンシャルは、まさにこの共創プラットフォームとしての未来を示唆しているのかもしれません。
未来への視点②:自治体の枠を超える「広域連携」による生存戦略
飯島氏が強調したように、中標津の発展は決して中標津町単独で成し遂げられたものではなく、別海町、標津町、羅臼町といった広大な根釧地域全体の存在があってこそでした。
「中標津が中標津のために頑張るのは当たり前。中標津が周りのために何か役割が果たせるような場面がこれからもあるんじゃないか。」
飯島氏のこの言葉は、これからの地方が取るべきスタンスを象徴しています。
人口減少と高齢化が急速に進む日本において、単一の自治体が全ての行政サービスや地域機能を維持していくことは、ますます困難になります。だからこそ自治体の枠組みを超えた「広域連携」が不可欠です。
観光資源の共同プロモーション、産業連携による新商品開発、医療や防災体制の相互補完…。
中標津が持つ「ハブ機能」を活かし、周辺地域と戦略的に連携していくことで、道東エリア全体の魅力と持続可能性を高めていくことができるはずです。
それぞれの地域の強みや役割を認識し、相互に補完し合いながら地域全体として価値を高めていく。これは企業経営におけるアライアンス戦略にも通じる考え方です。
自治体間のプライドや縦割りを乗り越え、いかに効果的な連携体制を構築できるかが、今後の地域経営の鍵を握ると言えるでしょう。
未来への視点③:「余白」と「定常」が生み出す、しなやかな強さ(レジリエンス)
そして、この対談が最も力強く提示したのが「ほどほど」「定常」「余白」といった、従来の成長・拡大志向とは異なる価値観の重要性でした。
経済成長だけを追い求めるのではなく、自然との調和の中で身の丈に合った豊かさを追求する「定常型」の社会。効率や生産性だけでなく、時間的なゆとりや人間的な繋がり、そして「何もない」ことの価値を再評価する視点。
一見すると後ろ向きにも捉えられかねないこれらの価値観が、実は予測困難な未来を生き抜くための「レジリエンス(回復力・しなやかさ)」に繋がっているのではないか、と対談は示唆します。
- 災害への備え: 広大な土地や使われていない空間(原っぱ)といった「余白」は、いざという時に避難場所や支援拠点として機能するかもしれない。(飯島氏)
- 変化への適応力: 過度な開発や特定の産業への依存を避ける「ほどほど」のあり方は、社会経済状況の変化に対する柔軟な適応力を高めるかもしれない。(加藤氏)
- 人間性の回復: 効率化やスピードばかりが求められる社会の中で、「余白」や「遊び心」を取り戻すことが、人々の精神的な豊かさや創造性を育むかもしれない。
レジリエンスとは、単に災害からの復旧能力だけでなく社会経済的な変化やストレスに対して、しなやかに適応し、持続的に発展していく能力を指します。中標津が(意図せずとも)示している「ほどほど」で「余白」のあるあり方は、まさにこのレジリエントな地域社会の一つの姿と言えるのかもしれません。
あなたの地域の未来を考えるヒントとして
加藤浩嗣教授と飯島実氏による「中標津モデル」を巡る対話は、中標津という一つの町の事例研究であると同時に、これからの日本の地域づくりに対する普遍的な問いを私たちに投げかけます。
- あなたの地域にとっての、本当の「豊かさ」とは何でしょうか?
- 経済的な成長以外にどのような価値を大切にしたいですか?
- その地域ならではの歴史や地理、文化は、未来に向けてどのような可能性を秘めているでしょうか?
- 未来の世代のために、私たちはどのような「余白」を残し、繋いでいくべきでしょうか?
中標津という「最果て」とも言われる場所から見えてきた可能性は、決して辺境の特殊事例ではありません。
むしろ、日本全国の地域がそれぞれの個性を活かしながら、持続可能で人間らしい未来を築いていくための貴重なヒントに満ちています。
この対談が、皆さんと共に地域の未来を考え、創造していくための一歩となることを願ってやみません。
◁◀◁(特集 第4回を戻る)
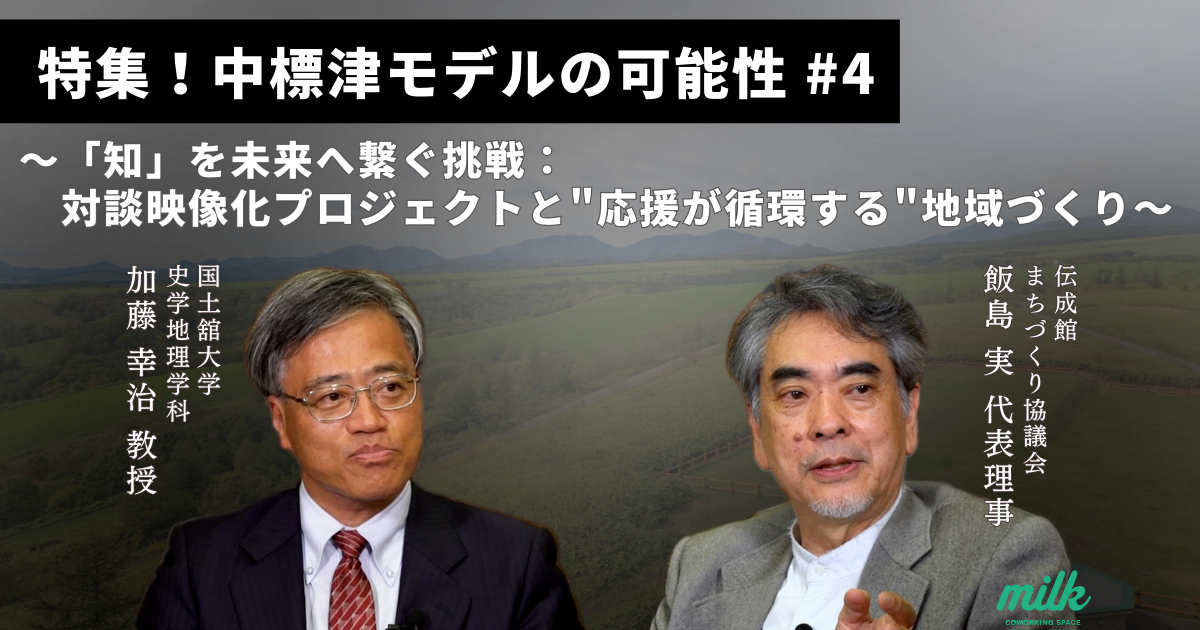
本記事は、2022年9月9日に北海道中標津町の「伝成館」にて行われた、国士舘大学 加藤幸治教授とNPO法人伝成館 飯島実理事長による対談「中標津モデルを経済と歴史で語る会」(主催:コワーキングスペースmilk / 株式会社しるべ)の内容に基づき構成しています。対談の記録映像制作にあたっては、クラウドファンディングを通じて全国26名の方々から18万3千円のご支援をいただきました。心より感謝申し上げます。
▼対談の全貌はこちらの動画でご覧いただけます!

北海道中標津町を拠点に「最果てを、最先端に」をビジョンとして活動。
コワーキングスペース運営を軸に旅行サービス手配業、まちづくり事業など、地域をフィールドとした様々な実験・プロジェクトを展開しています。

中標津町のコワーキングスペース。
仕事、勉強、打ち合わせ、地域との交流拠点として、どなたでもご利用いただけます。
【営業時間】年中無休 / 6:00〜22:00
【住所】北海道標津郡中標津町東3条北1-6 東龍門2F