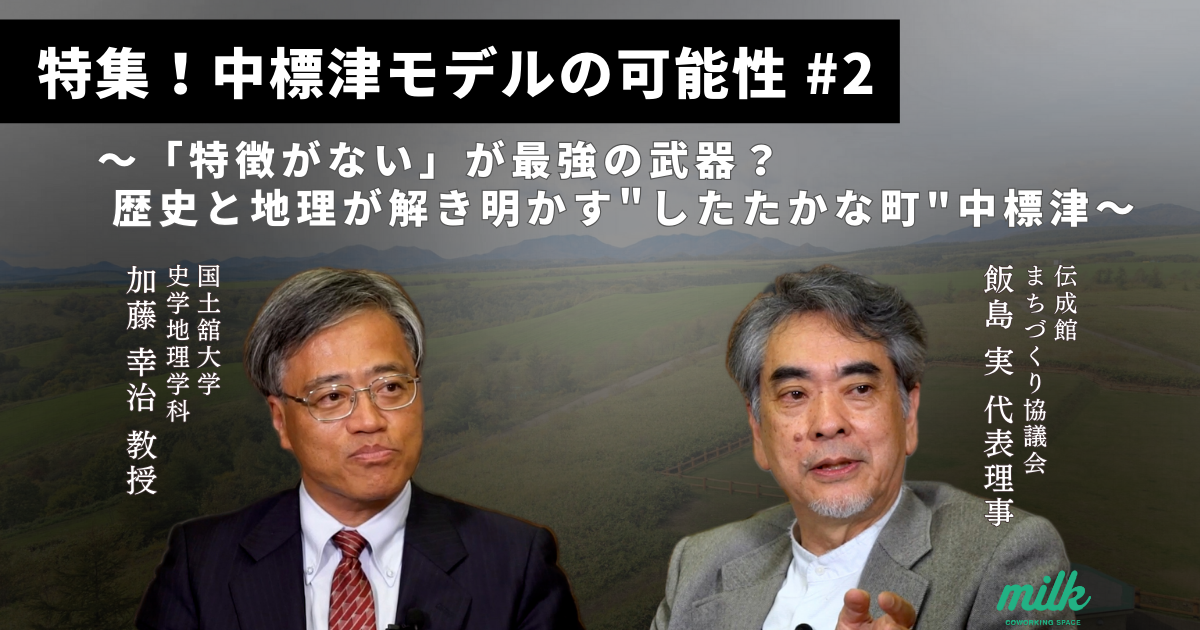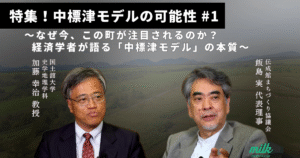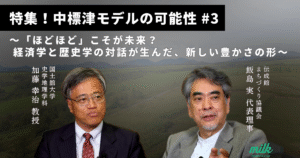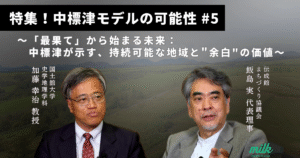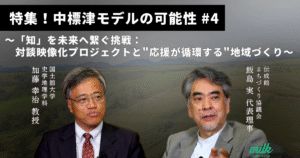経済地理学の視点から見て、人口減少時代の日本の地方都市にとって参考になるかもしれない「中標津モデル」。そのユニークな都市構造は、前回(特集#1)で見たように、コンパクトシティ政策とも共鳴する効率性や利便性を備えています。
しかし、その成り立ちは本当に「偶然」の産物なのでしょうか?
そして、その価値は「効率性」だけにあるのでしょうか?
本特集第2回は、中標津の歴史と地理を知り尽くすNPO法人伝成館(でんせいかん)理事長・飯島実氏の言葉を手がかりに、この町の持つもう一つの顔、そしてデータだけでは見えてこない「中標津らしさ」の源泉を探っていきます。
そこに見えてきたのは、一見「特徴がない」ように見えるこの土地に秘められた、したたかな生存戦略でした。
飯島氏の視点①:「特徴がない」「中心がない」ということの強み?
「中標津の最大の特徴は、特徴がないところ。それとね、中心地がないところ」
対談の冒頭、飯島氏が放ったこの言葉は加藤教授が分析した「中心性」とは一見、矛盾するように聞こえます。
しかし、飯島氏はこの「なさ」にこそ、中標津のユニークな価値があると言います。
他の多くの町が持つような強力な観光資源(有名な温泉や景勝地など)やランドマーク(歴史的な城郭やタワーなど)が中標津にはありません。「せいぜい開陽台くらいかな?」と飯島氏は笑います。
しかし、だからこそ特定のイメージに縛られず、訪れる人それぞれが自由に価値を見出すことができる「懐の深さ」があるのではないか、と示唆します。
同様に「町の中心」も時代と共に変遷してきました。かつての駅前、役場周辺、あるいは銀行のある交差点…。
しかし飯島氏は「今の中心は、昔の駅の跡地…つまり『何もない原っぱ』だと思っているんですよ」と語ります。
「夏祭り、冬祭りには、いろんな地域から人が集まってくる。何もないからこそ、みんなが集まれる。そこにこの町の役割がある」
大都市から見れば、何もない広大な原っぱがあること自体が、計り知れない贅沢であり、多様な可能性を秘めた「余白」なのです。
さらに飯島氏は「ないもの」の価値として「渋滞がない、熱帯夜がない、シロアリがいない、ゴキブリもいない…そして、あまり知られていないけれど飛行機雲がない」ことを挙げます。
北方領土問題の影響で、上空を国際線が通過しない、いわば「行き止まり」の空。それが、この地域の静けさや独特の空気感に繋がっているのかもしれません。
飯島氏の視点②:一般的な「北海道」とは違う? 中標津の特異な成り立ち
飯島氏は、中標津の歴史を紐解く上で一般的な「北海道」のイメージ…例えば、アイヌ文化、炭鉱、鉄道…といった要素がこの地域では希薄である点も指摘します。
「ここはアイヌのコタン(集落)として定住されていた場所ではなかった。炭鉱もない。そして鉄道も、比較的早い段階で廃止し、『空(空港)』を選んだ」。
こうした「北海道らしくなさ」が、中標津独自の発展経路…例えば、加藤教授が指摘した「商業中心」の性格や「内発的発展」(地元資本が地域経済を支える構造)…にどう影響してきたのか。
飯島氏の言葉は、私たちがステレオタイプで地域を見てしまうことへの警鐘を鳴らします。
飯島氏の視点③:開拓の歴史と、景観に込められた「意図」を読む
中標津の歴史は明治期からの根釧原野開拓と切り離せません。
飯島氏はこの地に最初に拠点を置いた農事試験場(現・伝成館)が、単なる中標津のためではなく、広大な原野全体の開拓を見据えた拠点であったことを強調します。そして、その開拓を主導した人々の中には、近江商人の血を引く者やアメリカまで学びに行った発明家のような、先見性と行動力を備えたパイオニアたちがいたことを明らかにします。
さらに飯島氏は、自身の航空分野への知見も活かしながら中標津の景観…特に格子状防風林や町の区画…に、単なる偶然や合理性だけでは説明できない、深い「意図」が隠されている可能性を示唆します。
「基線が国後島の茶々岳を指している」「不自然な林の配置が旧軍の滑走路への目印になっているように見える」「防風林の対角線が4000m級滑走路にぴったり収まる」「リンドバーグがニューヨークと羽田を結ぶ最短ルートとしてこの上空を通過した」「スターリンがこの地を欲しがっていた」…真偽のほどは更なる研究を待つとしても、飯島氏が語るこれらのエピソードは、中標津という土地が持つ歴史的・地理的な重要性とそこに込められたかもしれない壮大な計画への想像力を掻き立てます。
飯島氏の視点④:「ほどほど」を支える自然環境と、未来への「余白」
対談の終盤、飯島氏は中標津の「ほどほど感」の価値を強調します。
「ここの雪とか寒さとか、この『ほどほど』というか、かなりの厳しさがあるおかげでね、ほどほどのところにこの地域が収まっていると思う。良すぎるとね、とかく良くないことが起こっちゃう」。
そして、その「ほどほど」の暮らしを支えているのが豊かな自然環境そのものである、と。
特に防風林がもたらす「日陰」の効果は絶大で、ヒートアイランド現象とは無縁の、穏やかで安心できる気候を生み出している。また、武佐岳(むさだけ)という美しい山が常にランドマークとして存在することも、人々の「安心感」に繋がっているのではないか、と考察します。
さらに、広大な土地や無料駐車場に象徴される物理的な「余白」こそが、この町の豊かさの本質であり、将来、予期せぬ災害などが起こった際に、周辺地域をも受け入れる「セーフティネット」としての役割を果たす可能性すら秘めている、と飯島氏は語ります。「余裕とか余白とかって言えるようなことがあるのは本当は大事なんですけど、なんかつい忘れてしまいがちなものなので」。
経済合理性とは異なる尺度で、中標津のユニークな価値を解き明かした飯島氏。「特徴がないこと」「中心がないこと」「北海道らしくないこと」「ほどほどであること」「余白があること」…。
一見ネガティブに捉えられがちな要素が、実はこの町のレジリエンス(しなやかな強さ)や持続可能性、そして未来への可能性の源泉となっているのかもしれません。
次回【特集#3】では、加藤教授の経済学的視点と飯島氏の歴史・地理的視点が対談の中でどのようにぶつかり合い、響き合い、そして未来の地域づくりへのどのような示唆を生み出したのか、その化学反応の核心に迫ります。
(特集 第3回へつづく)▶▷▶
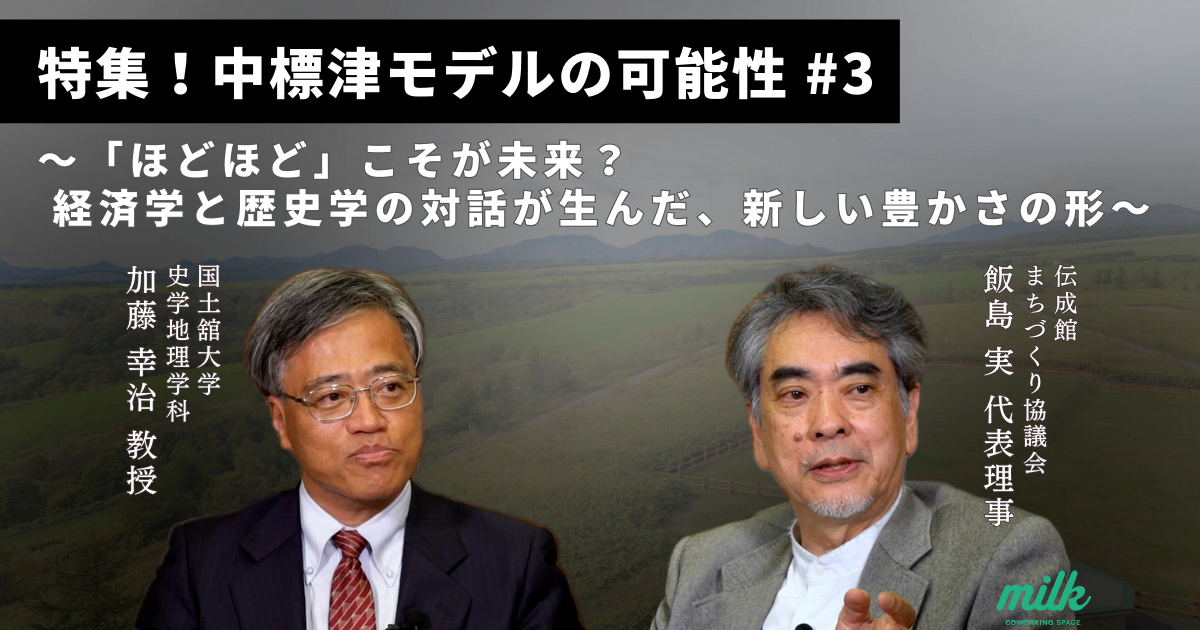
◁◀◁(特集 第1回に戻る)
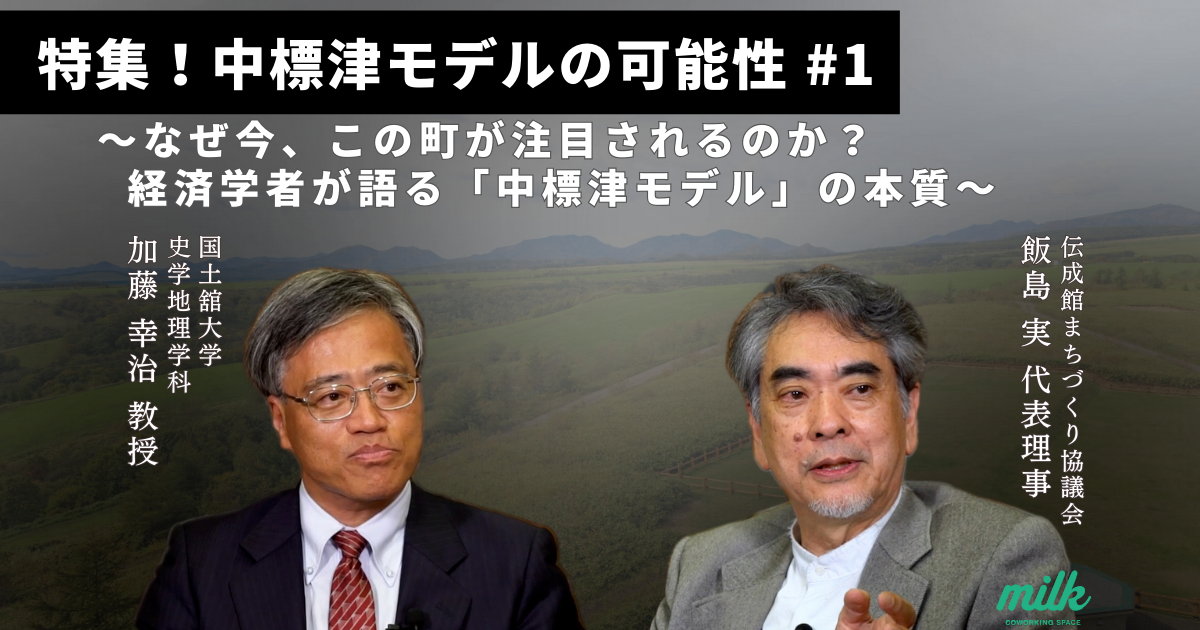
本記事は、2022年9月9日に北海道中標津町の「伝成館」にて行われた、国士舘大学 加藤幸治教授とNPO法人伝成館 飯島実理事長による対談「中標津モデルを経済と歴史で語る会」(主催:コワーキングスペースmilk / 株式会社しるべ)の内容に基づき構成しています。対談の記録映像制作にあたっては、クラウドファンディングを通じて全国26名の方々から18万3千円のご支援をいただきました。心より感謝申し上げます。
▼対談の全貌はこちらの動画でご覧いただけます!

北海道中標津町を拠点に「最果てを、最先端に」をビジョンとして活動。
コワーキングスペース運営を軸に旅行サービス手配業、まちづくり事業など、地域をフィールドとした様々な実験・プロジェクトを展開しています。

中標津町のコワーキングスペース。
仕事、勉強、打ち合わせ、地域との交流拠点として、どなたでもご利用いただけます。
【営業時間】年中無休 / 6:00〜22:00
【住所】北海道標津郡中標津町東3条北1-6 東龍門2F