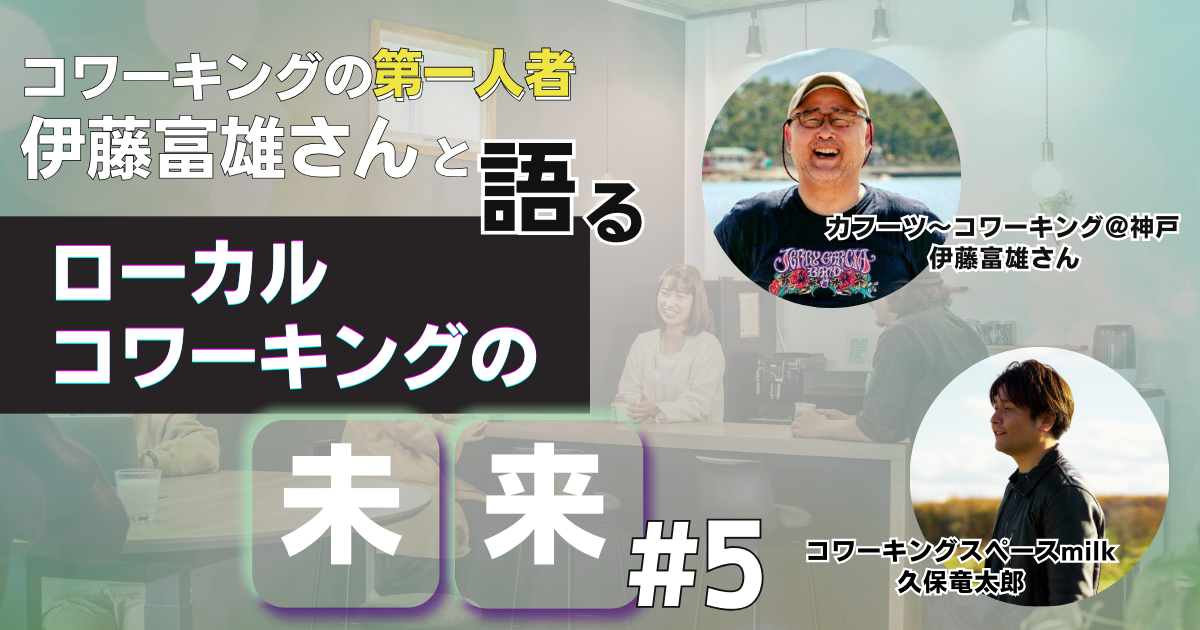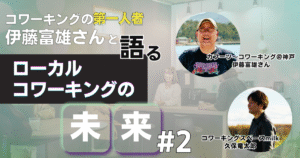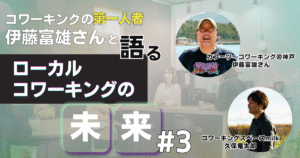第5回(最終回):未来への実験室 – ローカルから始まる新しい働き方と暮らし
北海道中標津町のコワーキングスペース「milk」運営者 久保竜太郎氏と、業界の第一人者である伊藤富雄氏との対談を通して、私たちはローカルコワーキングが秘める多大な可能性を探ってきました。
辺境の地に灯った一つの「場」がいかにして地域内外の人々を繋ぐ「ハブ」となり、観光や情報発信といった具体的な地域課題解決に挑む「プラットフォーム」へと進化しようとしているのか。その軌跡は多くの示唆に富んでいました。
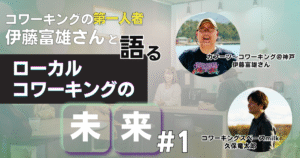
最終回となる今回はmilkが今後どのような未来を描き、挑戦を続けていこうとしているのか、そしてその先にローカルコワーキングが私たちの働き方や暮らし、ひいては地域社会全体にもたらしうる変革の可能性について、考察を深めていきたいと思います。
未来への布石:具体的なアクションプラン
対談の終盤、久保氏はmilkの今後の展開について、具体的なアクションプランを語っています。それはこれまでの試行錯誤から得られた学びを着実に事業として、そして地域への貢献として結実させようという強い意志の表れです。
まず「観光」分野においては開発・実験してきた高付加価値な体験コンテンツを本格的に商品化し、営業活動を開始する段階にあります。
特に、企業や各種団体の「視察旅行」市場に注目している点は興味深いところです。地域ならではの学びや体験を求める視察旅行のニーズに対し、「この漁師さんに会いに来てください」「この酪農家さんの話を聞きに来てください」といった、milkだからこそ提供できるユニークなプログラムを提案していく。これは地域の魅力を新たなターゲット層に届け、経済的な効果を生み出すための戦略的な一手と言えるでしょう。
そして「コミュニティ・起業支援」の領域では、クラウドファンディングなどを活用した企画創出の仕組みを「ゲーム化」し、誰もがアイデアを形にしやすい環境を整えたいと考えています。
「プレゼンをして企画化して、お金を集めてダメだったらドンマイ、ブラッシュアップしましょう、だし、集まったらこれやってみましょう」。そんな挑戦と学びのサイクルが日常的に回る「インキュベーションセンター」としての機能強化。
これは地域に新しいプレイヤーを呼び込み、内発的な活性化を促すための重要な布石です。
残された課題と向き合い続ける覚悟
もちろん輝かしい未来だけを見据えているわけではありません。久保氏はローカルコワーキングが抱える根本的な課題についても、冷静な認識を示しています。
利用者をいかに増やし、維持していくか。「集まる理由」をどう創出し続けるか。
これはmilkだけでなく、全国のローカルコワーキングスペースが共通して向き合うべき、永遠のテーマなのかもしれません。
「作業しに来る人」だけでなく、「そこにいる人に会いに来る」「何か面白いことが起こりそうだから行ってみる」。そう思わせる求心力を維持・向上させていく必要性を、久保氏は強く認識しています。
コワーキングスペースは「ラボ(実験室)」である
対談の最後に、伊藤氏から「久保さんにとってコワーキングとは何か?」という問いが投げかけられました。それに対する久保氏の答えは、非常に示唆に富むものでした。
「ラボです。研究室みたいな感じです。僕は」
この言葉はmilk、そして久保氏自身のあり方を象徴しているように思えます。
コワーキングスペースは完成された答えを提供する場所ではなく、むしろ未知なる可能性を探求し、試行錯誤を繰り返す「実験室」である、という捉え方です。
新しいアイデアを試行錯誤し、時には失敗もしながら地域のための価値創造に挑戦していく場。
基礎研究のように、すぐには成果が出なくても重要な役割。
例えば専門学校生と共にアイデアを出し合い、クラウドファンディングで資金と共感を集めて実現にこぎつけた『高校生デート企画』のような試みも、まさにこの『ラボ』が生み出した具体的な実験の一つと言えるでしょう。それは新しいPRの手法を探る実験であり、若者支援のあり方を問う実験であり、そして地域を巻き込むプロセスそのものの実験でもありました。
伊藤氏の「実証実験」という言葉との共鳴。そして成功だけでなく失敗も含めた実験の結果を記録し、共有することの重要性。milkの活動は、まさにその実践と言えます。
ローカルコワーキングが拓く未来
中標津のmilkの挑戦を通して見えてきたのは、ローカルコワーキングスペースが持つ、計り知れない可能性です。
- 多様な人々を繋ぎ、新たな関係性を育む「ハブ」としての機能。
- 地域が抱える経済的・社会的課題に対し、具体的な解決策を生み出す「プラットフォーム」としての機能。
- そして、未来への可能性を信じ、挑戦と失敗を繰り返しながら新しい価値を創造していく「ラボ(実験室)」としての機能。
これらを統合し、地域全体の対話と協働を促進する「街のファシリテーション機能」こそが、ローカルコワーキングスペースがこれから担っていくべき、最も重要な役割なのかもしれません。
それは単に新しい働き方を提供するだけでなく、私たちの暮らし方、地域との関わり方、そして未来の社会のあり方そのものを足元から変えていく力を持っているのではないでしょうか。
中標津という「辺境の地」で灯った小さな火は、今、ローカルの未来を照らす、大きな可能性の光へと変わろうとしています。久保竜太郎氏とmilkの「実験」が全国の地域やコワーキングスペースにとって、一つの希望となり、次なる挑戦への勇気を与えることを期待し、本シリーズを締めくくりたいと思います。
彼らの今後の活動に、引き続き注目していきましょう。
◁◀◁【第4回に戻る】
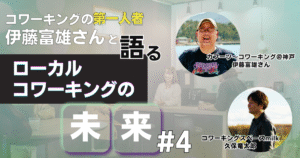
▼対談の全貌はこちらの動画でご覧いただけます!

北海道中標津町を拠点に「最果てを、最先端に」をビジョンとして活動。
コワーキングスペース運営を軸に旅行サービス手配業、まちづくり事業など、地域をフィールドとした様々な実験・プロジェクトを展開しています。

中標津町のコワーキングスペース。
仕事、勉強、打ち合わせ、地域との交流拠点として、どなたでもご利用いただけます。
【営業時間】年中無休 / 6:00〜22:00
【住所】北海道標津郡中標津町東3条北1-6 東龍門2F
カフーツ伊藤さん
日本最初のコワーキング「カフーツ」主宰/経産省認可法人コワーキング協同組合代表理事/コワーキングツアー/コワーキングマネージャー養成講座/Beyond the Coworking〜移働の時代〜 など
また「Beyond the Coworking 〜移働の時代〜」では、2010年に日本初のコワーキングスペースを開設したカフーツ伊藤が、これからのコワーキングとその周辺を軸に、「移働」と「共創」による新しい働き方、新しい生き方、引いては新しい社会についての情報と知見、アイデアを共有しつつ、共に学び、共創し、各自の日々の活動に活かすことを目的としたコミュニティです。