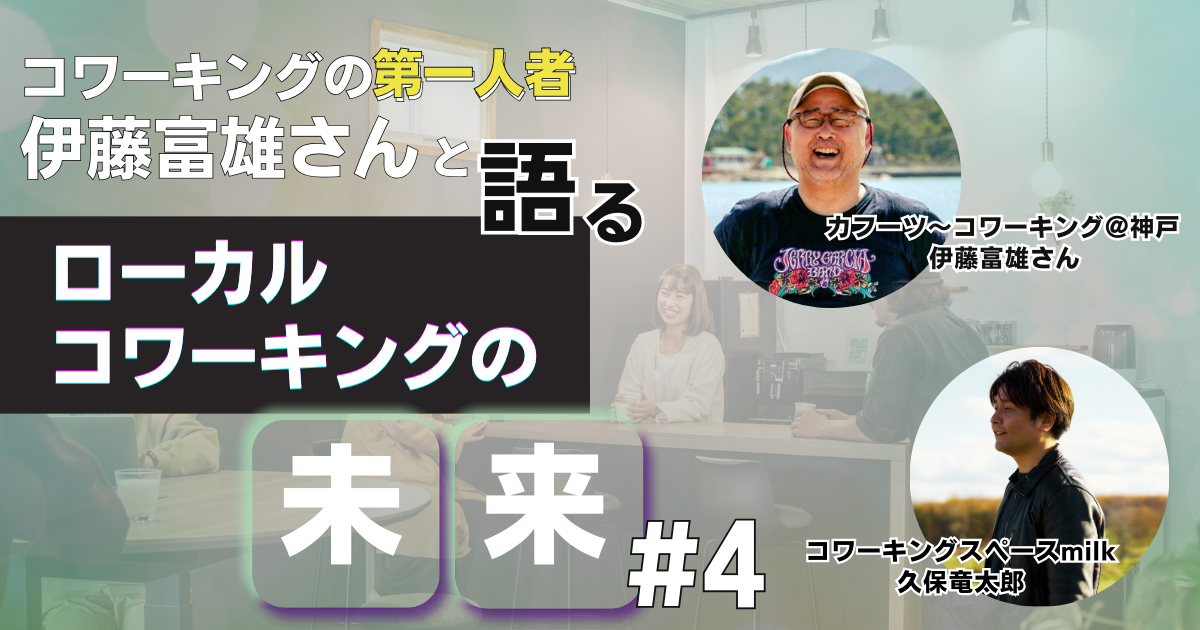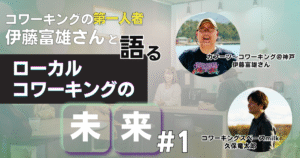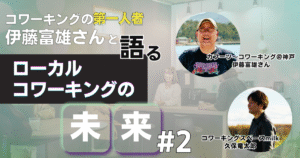第4回:地域課題への挑戦 – 観光、情報発信、そして「街のファシリテーション」
前回、私たちはコワーキングスペース「milk」が単なる物理的な場を超え、地域内外の人々や多様な知を結びつける「ハブ」としての可能性を模索している姿を見てきました。
「よそ者」の視点を活かし、関係人口を創出し、「知の再結合」を促す。その試みは、ローカルコワーキングスペースが地域社会で果たしうる、新たな役割を示唆していました。
しかし、理想を追求するだけでは事業として、そして地域への貢献活動として持続可能性を確保することは困難です。特にリソースの限られるローカルにおいては、経済的な基盤の確立と具体的な地域課題へのコミットメントが不可欠となります。
第4回となる今回は、milkが直面した運営上の課題とそれを乗り越えるために選択した具体的なアクション、すなわち「観光」と「情報発信」への挑戦に焦点を当てます。
一見、異なる分野に見えるこれらの取り組みの根底には久保竜太郎氏が見出すコワーキングスペースの、ある本質的な機能がありました。
課題解決への挑戦①:観光 – 新しい価値を創造し、経済を動かす
「儲からないんですよね。(中略)コワーキングスペースどこまでやる?みたいな話になるわけです。いいことやってんのわかるんだけど…」
対談の中で久保氏は、コワーキングスペース運営の経済的な厳しさを率直に語ります。
地域に貢献する活動であっても、それが持続可能でなければ意味がない。milkを引き継ぎ、独立した久保氏にとって経済的自立は避けて通れない課題でした。「このまま(以前と)同じようにやってても普通に潰れるだけだから」。
そこで彼が活路を見出したのが「観光」でした。
道東エリアが持つ高いポテンシャルと、既存の観光モデル(集客型、画一的)への疑問。そして何より、自身の体験(ヒッチハイク等)から得た「地域とのリアルな関わりこそが旅の価値」という確信。これらを掛け合わせ「地域との信頼関係に基づいた、高付加価値な体験を提供する」という新しい観光の形を構想します。
その実現のために彼は「旅行サービス手配業」の資格を取得。
これは地域で独自に企画・造成した体験プログラムを旅行会社などに販売(卸売)するための専門的な許可です。
これによりmilkは単に場を提供するだけでなく、地域の隠れた魅力を掘り起こし、それを価値ある観光コンテンツとして外部に繋ぎ、経済的な流れを生み出す主体となることを目指し始めたのです。
これは単なる事業の多角化ではありません。
地域の資源を守りながら、その価値を正しく伝え、持続可能な形で外部と共有していく。ローカルが抱える「経済的自立」と「地域資源の活用」という二つの課題に対する、コワーキングスペースならではの挑戦と言えるでしょう。
課題解決への挑戦②:情報発信 – 民主主義の土壌を耕す
もう一つの特筆すべき挑戦が「情報発信」の領域、特に地域の意思決定プロセスに関わるテーマへの取り組みです。昨年夏、中標津町で行われた町議会議員選挙の際に、milk(当時はまだ久保氏が運営に関与)が中心的な役割を果たし、選挙特番が制作・配信されました。
なぜ、コワーキングスペース運営者が選挙特番を手がけることになったのか? きっかけは、久保氏自身が感じた選挙における「情報の分かりにくさ」でした。「誰が出るのかわからんし、その人がどういうふうにやろうとしてるのか、もうマジでわからない」。特に選挙活動期間が短い地方選挙においては、有権者が十分な情報に基づいて判断することが困難な状況がある、という問題意識です。
当初は軽い気持ちで「候補者を集めた討論会をやれば?」と提案したところ、逆に「ぜひやってほしい」と周囲から期待され、引くに引けなくなった、というのが真相のようですが(笑)。公職選挙法の壁や様々な調整を経て、最終的にはローカルFM局「FMはな」との連携により、候補者へのアンケート結果を基に有識者が議論するという形の番組が実現しました。
この取り組みは地域の重要な意思決定プロセスである選挙において、情報の透明性を高め、有権者(特に、情報から遠ざかりがちな若い世代)の関心を喚起するという、極めて公共性の高い試みでした。
しかし久保氏はこの特番だけでは不十分だと感じています。「日々の議会のことをあの知ってないと、そもそもダメだったねって反省もありまして」。
現在、彼はFMはなと共に定例会ごとに行われる議会の内容を分かりやすく解説・議論する、継続的な「議会番組」の制作を構想しています。これは単発のイベントを超え、地域の情報流通のあり方そのものに働きかけ、住民の政治参加を促す「民主主義の土壌を耕す」挑戦と言えるのではないでしょうか。
コワーキングスペースの本質:「街のファシリテーション機能」
「観光企画」と「選挙・議会に関する情報発信」。一見すると、これらは全く異なる分野の取り組みに見えます。しかし、久保氏はこの二つの活動の根底に共通するコワーキングスペースの役割を見出しています。それが「街のファシリテーション機能」です。
「なんか多分、街としてのファシリテーションを担う機能だと思うんですよ。コワーキングスペースって。(中略)直接混ぜたら危ないから。いや、こっちはこういう事情で、こっちはこういう事情だから、こういうふうに交わらないルールのが一番ベストですよねっていうのを全部やるのが、多分コワーキングスペース」
地域住民、事業者、観光客、行政、議会…。地域には様々な立場や利害関係を持つ人々が存在します。それぞれの思いや主張がぶつかり合い、時に停滞や対立を生むことも少なくありません。
コワーキングスペースはその「間」に入り、中立的な立場で対話を促進し、それぞれの事情を理解した上で課題を整理し、建設的な解決策や新たな協力関係へと導く「調整役」「触媒役」としての役割を担うことができるのではないか。久保氏はそう考えているのです。
観光企画においては地域の事業者(漁師など)と外部の旅行者の間に入り、「失礼なく、お互いが気持ちよく関われるルール」を作り、特別な体験を実現する。
議会番組においては行政や議会と町民の間に入り、一方的な批判ではなく、「こういう前提で、こういうルールで話し合いましょう」と、建設的な対話の場をデザインする。
これらはまさに、高度なファシリテーション能力が求められる営みです。そして、多様な人々が集い、情報が交差するコワーキングスペースは、その能力を発揮する上で、非常に有利なポジションにあると言えるでしょう。
ローカルの課題解決プラットフォームへ
milkの挑戦はコワーキングスペースが単なるワークスペースや交流の場に留まらず、観光振興、情報流通の改善、住民参加の促進、合意形成といった、ローカルが抱える複合的な課題に対する具体的な解決策を生み出す「プラットフォーム」となり得る可能性を示しています。
それは「街のファシリテーション機能」という、コワーキングスペースの新たな、そして極めて重要な存在意義を提示していると言えるのではないでしょうか。
次回(最終回)はこうした活動を通してmilk、そして久保竜太郎氏が描く未来像とローカルコワーキング全体が持つ可能性について、考察を深めていきます。
【第5回へ続く】▶▷▶
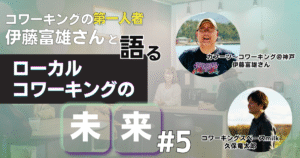
◁◀◁【第3回に戻る】
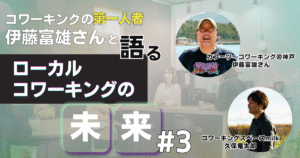
▼対談の全貌はこちらの動画でご覧いただけます!

北海道中標津町を拠点に「最果てを、最先端に」をビジョンとして活動。
コワーキングスペース運営を軸に旅行サービス手配業、まちづくり事業など、地域をフィールドとした様々な実験・プロジェクトを展開しています。

中標津町のコワーキングスペース。
仕事、勉強、打ち合わせ、地域との交流拠点として、どなたでもご利用いただけます。
【営業時間】年中無休 / 6:00〜22:00
【住所】北海道標津郡中標津町東3条北1-6 東龍門2F
カフーツ伊藤さん
日本最初のコワーキング「カフーツ」主宰/経産省認可法人コワーキング協同組合代表理事/コワーキングツアー/コワーキングマネージャー養成講座/Beyond the Coworking〜移働の時代〜 など
また「Beyond the Coworking 〜移働の時代〜」では、2010年に日本初のコワーキングスペースを開設したカフーツ伊藤が、これからのコワーキングとその周辺を軸に、「移働」と「共創」による新しい働き方、新しい生き方、引いては新しい社会についての情報と知見、アイデアを共有しつつ、共に学び、共創し、各自の日々の活動に活かすことを目的としたコミュニティです。