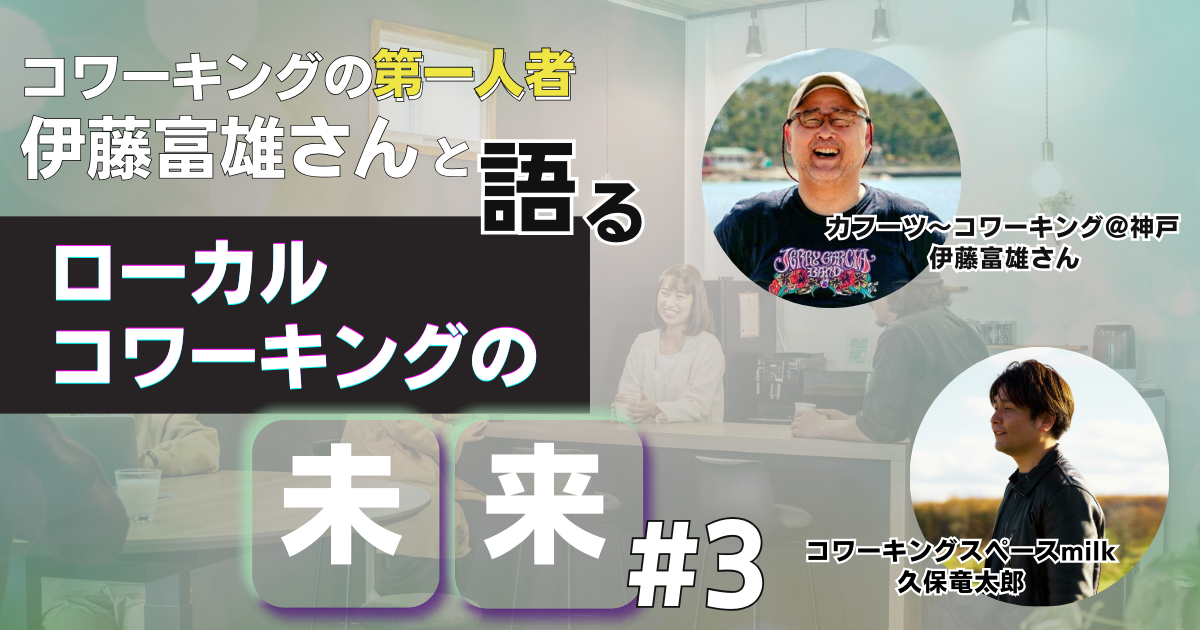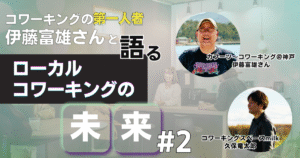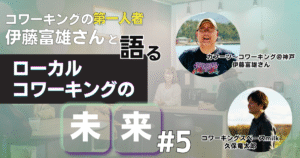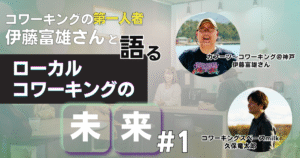第3回:越境するハブの可能性 – 地域と世界を繋ぐ「知の再結合」
前回、私たちはコワーキングスペース「milk」がテクノロジーの活用やイベント開催といった試行錯誤を経て「場」としての第一歩を踏み出した過程を見てきました。しかし、運営者の久保竜太郎氏の視線は単なる場所の運営に留まらず、より本質的な価値、すなわち人々が継続的に関わりたくなる「ここに来る理由」の創出へと向かっていました。
その根底にあるのは「外の人と中の人を混ぜる」という強い目的意識です。
ローカルが持つポテンシャルを解き放つためには時に外部の視点や知見、多様な価値観を取り込み、地域内部の資源と掛け合わせるプロセスが触媒となり得るのではないか。久保氏はその「混ぜ合わせる」ための結節点としての役割を、コワーキングスペースに見出していたのです。
第3回となる今回は、milkがどのようにして地域と外部を繋ぐ「ハブ」としての機能を模索し、実践しようとしているのか。そして、その先に目指す「知の再結合」とは何か。対談からその可能性を探ります。
ローカルに新しい風を:「よそ者」の視点がもたらす価値
久保氏は中標津という地域に対して深い愛情を持つ一方で、外部からの新しい視点や刺激が加わることで地域がさらに活性化する可能性があると考えています。地元の人々にとっては当たり前の日常や風景の中に、外部の人間だからこそ気づく未開発の価値や改善のヒントが眠っていることは少なくありません。
しかしその「外の目線」を地域がスムーズに受け入れ、活かすことは必ずしも容易ではありません。変化への抵抗感や見慣れない存在への警戒心が存在することも事実です。
だからこそ地域に根差しながらも、外部とのパイプを持つコワーキングスペースのような存在が両者の間の「翻訳者」や「緩衝材」として機能することが重要になります。milkはそのデリケートな役割を深く理解し、意識的に担おうとしていました。
実践例:SAGOJO連携 – 「お手伝い」が生む新しい関係性
その具体的な試みの一つが「SAGOJO(サゴジョウ)」との連携です。「地域のお手伝い(シゴト)をしながら旅をする」というコンセプトのプラットフォームであるSAGOJO。旅人は地域事業者の仕事を手伝う対価として報酬や滞在場所を得ながら、表面的な観光では得られない深い地域との関わりを体験できます。
久保氏はこの仕組みに着目し、milkがハブとなり、地域の事業者(前職の竹下牧場や、隣町・標津町の漁師など)と「お手伝いしたい旅人」を繋ぐ役割を買って出ました。
「地域の事業者と仲良くなり、こういうサービス(SAGOJO)があるから一緒に企画をしませんか、と提案する。そのためのハブとしてmilkを使ってほしい」と働きかけたのです。
この連携により、牧場の商品開発サポートやゲストハウスのDIYといった企画が実際に生まれました。これは単に労働力を提供する・されるという関係に留まりません。
旅人は地域のリアルな仕事や想いに触れ、事業者は外部の新鮮な視点やスキルに刺激を受ける。そして何より、その交流を通して人と人との間に信頼関係が醸成され、新たなアイデアやビジネスチャンスが生まれる土壌が育まれていくのです。
これは関係人口の創出や地域の人材不足といった課題に対する、非常に興味深いアプローチと言えるでしょう。
「知の再結合」へ:コワーキングスペースが起こす化学反応
SAGOJO連携のような取り組みは地域と外部を繋ぐ具体的なステップですが、インタビュアーの伊藤富雄氏は、その先にある、より本質的な価値として「知の再結合」という概念を提示します。
これはヴェネチア大学の教授が提唱した考え方に伊藤氏が着想を得たもので、地域内部に存在する知(知識、経験、文化、人脈)と外部から持ち込まれる新しい知(専門スキル、多様なネットワーク、異なる価値観)がコワーキングスペースという場で出会い、融合することで、単なる足し算ではない、新たな価値やイノベーションが生まれる、という考え方です。
近年、リモートワークの普及に伴い「ワーケーション」や「デジタルノマド」といった、場所に縛られずに働く人々が世界的に増加しています。彼らはかつてのツーリストとは異なり、多くの場合、高度な専門スキルや知識、そして多様な経験を持つ「ワーカー」です。
伊藤氏は、こうした新しいタイプの移動者たちが、特に日本のローカルに対して強い関心を抱いていると指摘します。彼らが求めているのは単なる観光地の訪問ではなく、地域の人々と交流し、その土地ならではの文化や課題に触れる「体験」であり、場合によっては自身のスキルを活かして地域に貢献したい、という想いを持っていることさえあります。
コワーキングスペースはこうした人々を地域に迎え入れ、彼らが持つ「知」と地域の「知」が出会うための、まさに最適な「触媒」となり得るのです。受け入れ窓口として機能するだけでなく、地域住民や事業者との橋渡し役となり、時には具体的な協働プロジェクトを生み出す起点となる。
これこそがローカルコワーキングスペースが担うべき、極めて重要な役割だと伊藤氏は説きます。
久保氏もこの「知の再結合」の考え方に強く共鳴しています。「地元の都合だったり、弱いポイントっていうのを理解した上で、こういうスキルを持った人がこういう風なところにポンってハマったら、この地域もっといいんじゃないか」。まさに外部の知見を地域の文脈に合わせて翻訳し、実装していくプロセスをイメージしているのです。
ただし、その際には「地元の人が嫌な感じにならないように、どう(化学反応を)起こすか」という、地域への深い理解と敬意に基づいた丁寧なファシリテーションが不可欠である、とも強調します。
外部の論理を一方的に持ち込むのではなく、あくまで地域主体で、内発的な変化を促していく。その繊細な舵取りこそが、コワーキングスペース運営者の腕の見せ所なのかもしれません。
結節点としてのコワーキングスペース
milkの試みはコワーキングスペースが単なる物理的な「場」の提供に留まらず、地域内外の人々、多様な知見や文化、そして新しい働き方と地域資源を結びつける「ハブ」あるいは「結節点」としての役割を強く意識していることを示しています。
それはローカルが抱える様々な課題に対し、外部の力も戦略的に取り込みながら地域の中から解決策や新たな価値を生み出していくための重要な社会的インフラとなり得る可能性を秘めているのです。
しかしその「ハブ」機能をより強化し、具体的な経済的価値や社会的インパクトへと繋げていくためには、さらなる戦略とアクションが求められます。
次回は、milkが「観光」や「情報発信」といった具体的な地域課題にどのようにアプローチし、コワーキングスペースとしての提供価値をさらに高めようとしているのか、その挑戦に迫ります。
【第4回へ続く】▶▷▶
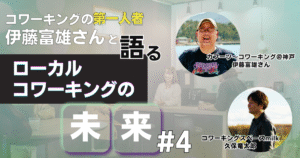
◁◀◁【第2回に戻る】
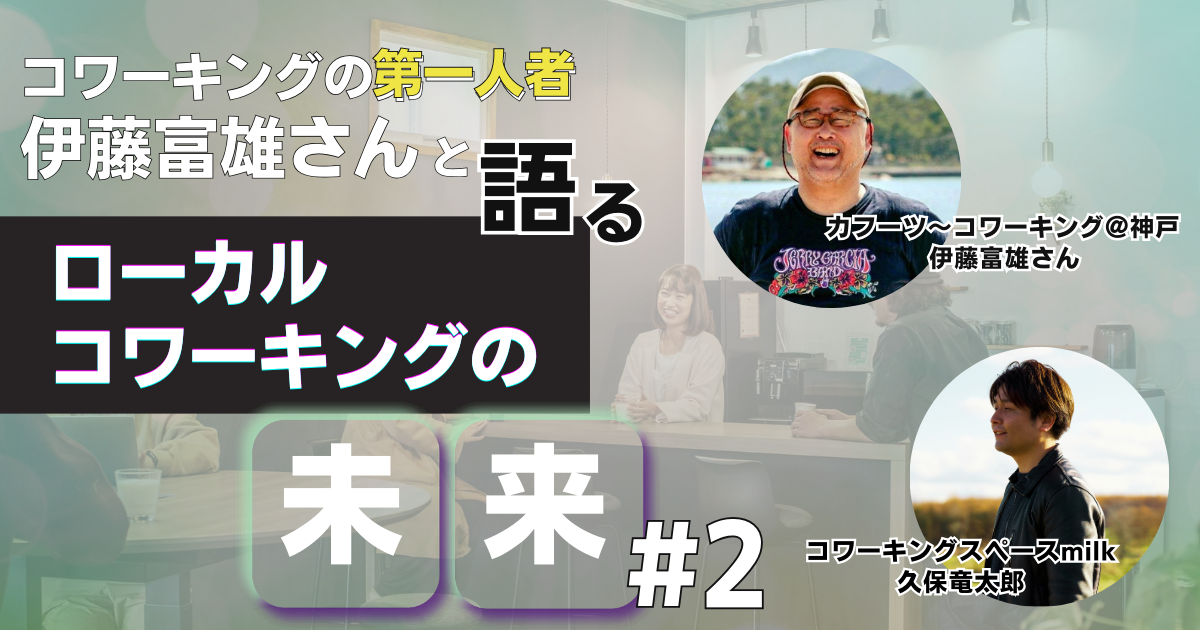
▼対談の全貌はこちらの動画でご覧いただけます!

北海道中標津町を拠点に「最果てを、最先端に」をビジョンとして活動。
コワーキングスペース運営を軸に旅行サービス手配業、まちづくり事業など、地域をフィールドとした様々な実験・プロジェクトを展開しています。

中標津町のコワーキングスペース。
仕事、勉強、打ち合わせ、地域との交流拠点として、どなたでもご利用いただけます。
【営業時間】年中無休 / 6:00〜22:00
【住所】北海道標津郡中標津町東3条北1-6 東龍門2F
カフーツ伊藤さん
日本最初のコワーキング「カフーツ」主宰/経産省認可法人コワーキング協同組合代表理事/コワーキングツアー/コワーキングマネージャー養成講座/Beyond the Coworking〜移働の時代〜 など
また「Beyond the Coworking 〜移働の時代〜」では、2010年に日本初のコワーキングスペースを開設したカフーツ伊藤が、これからのコワーキングとその周辺を軸に、「移働」と「共創」による新しい働き方、新しい生き方、引いては新しい社会についての情報と知見、アイデアを共有しつつ、共に学び、共創し、各自の日々の活動に活かすことを目的としたコミュニティです。