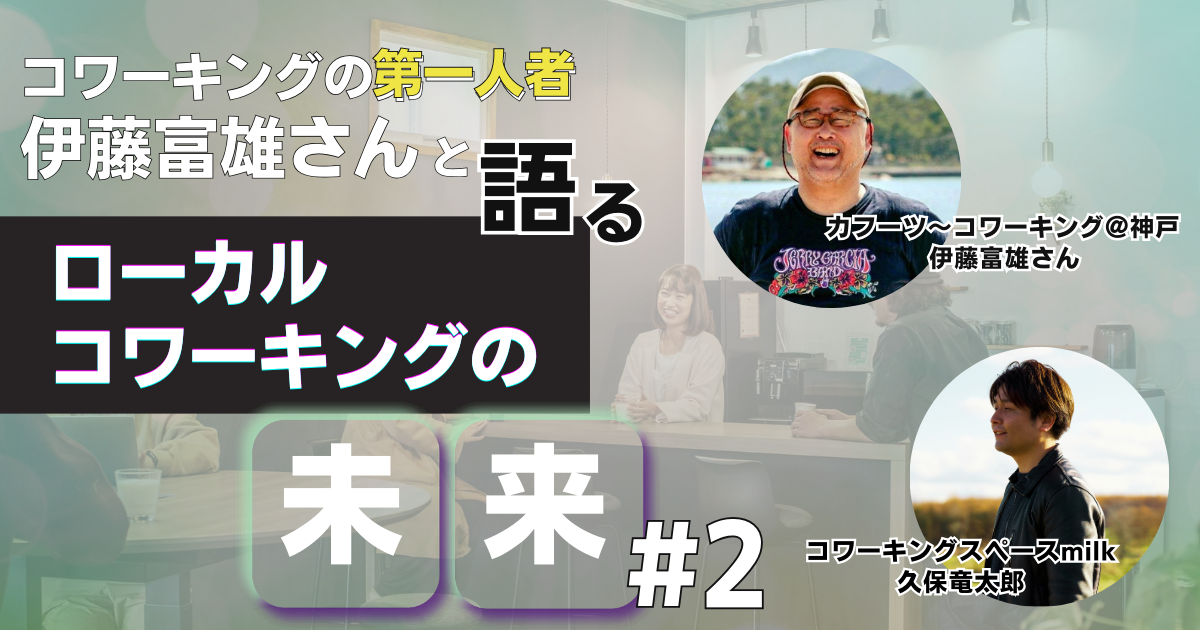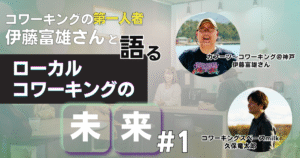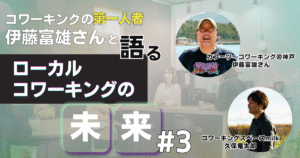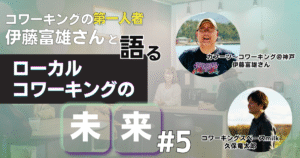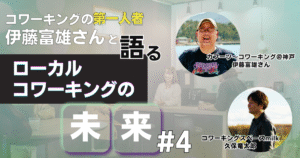第2回:場をデザインする試行錯誤 – 人を繋ぐための「仕掛け」とは?
前回、私たちは北海道中標津町に誕生したコワーキングスペース「milk」の背景にある物語を探りました。運営者である久保竜太郎氏のユニークな経歴、中標津という土地の個性、そして時代の要請が重なり合い、辺境の地に新たな「場」が灯ったことを見てきました。
しかし、場が生まれただけではその価値は十分に発揮されません。特に地域社会に深く根ざし、多様な人々を繋ぐ役割が期待されるローカルコワーキングスペースにとって「場をどうデザインし、運営していくか」は極めて重要な問いとなります。
物理的な空間としての快適さはもちろん、そこでの出会いや活動を促す「仕掛け」が求められるのです。
第2回となる今回はmilkが設立当初、どのような試行錯誤を経て「場」を形作ろうとしてきたのか、その具体的な運営方法や初期の取り組みに焦点を当てます。対談からは、ローカルならではの課題に直面しながらも知恵と工夫で道を切り拓こうとする運営者のリアルな姿が浮かび上がってきます。
テクノロジーと割り切りが生んだ「半・無人運営」
まず注目すべきはmilkの運営スタイルです。
対談の中で久保氏は「うちはあの、一応スマートロックで管理していてドロップインももちろん使えるんですけど、アプリで無人でもできるように設計してました」と語っています。
利用者は専用アプリをスマートフォンにインストールし、それを使ってドアの解錠から利用時間のカウント、そして決済までを行う。これは都市部のコワーキングスペースでは増えつつあるものの、ローカルではまだ珍しい仕組みかもしれません。
なぜ、この方式を採用したのか?
その背景には「僕が絶対入れないから」という、運営者自身の物理的な制約がありました。他の業務も抱える久保氏が常にスペースに常駐することは現実的ではない。この制約を前提とした上でテクノロジーを活用し、利用者の利便性を損なわずに運営できる方法を模索した結果が、この「半・無人運営」だったのです。
これは、ある意味で「コワーキングスペースにはコミュニティマネージャーが常駐し、人と人とを繋ぐべき」という理想像に対する現実的な回答であり、割り切りとも言えます。
しかしリソースの限られるローカルにおいては、こうした合理的な判断とテクノロジーの活用が、持続可能な運営のための鍵となる可能性を示唆しています。
場を温める初期戦略:社員利用とイベント開催
とはいえ、テクノロジーだけで「場」が自然に温まるわけではありません。設立当初、中標津という地域において「コワーキングスペース」という概念自体の認知度は ほぼゼロに等しかったと言います。
「箱作ったってしゃあないんやなっていうのが、ものの見事にそうだなって」と久保氏が語るように、まずは人々がmilkを訪れる「理由」を作る必要がありました。
その初期戦略として、二つのアプローチが取られました。
一つは運営母体(当時)であった竹下牧場の社員が、作業場所としてmilkを利用すること。
誰もいない空間ではなく、常に誰かが活動している気配があることで、場としての最低限の「温度」を保つ狙いがあったのでしょう。
そしてもう一つが「イベント開催」です。
インタビュアーの伊藤氏も自身の経験を踏まえ「(コワーキングスペースが)できたっていうのはネットで知ってた。だけども、そこへ自分が出かけていくきっかけというのが全然わからなかった」「イベントだったら自分も参加したし…」と語るように、イベントは地域の人々にとってコワーキングスペースを訪れる最初の、そして最も分かりやすいきっかけとなります。
milkでも「税理士さんと弁護士さんが来て、なんか雑談勉強会みたいなのをするからおいで」(久保氏)といった専門家を招いた学びの場や、地域に新しくできた日本語学校の留学生と地元民の交流を目的とした飲み会企画(これもクラウドファンディング的に資金を集めたそうです)など、多様なイベントを開催しました。
これらの試みはmilkという場の存在を地域に知らせ、様々なバックグラウンドを持つ人々を引き合わせる上で、重要な役割を果たしたことは間違いありません。
「ただの箱」で終わらないために:「ここに来る理由」の模索
社員による利用と多様なイベント開催。これらによって、milkは物理的な「箱」としてだけでなく、人々が集う「場」としての第一歩を踏み出しました。
しかし、久保氏はそれで満足していたわけではありません。
「やみくもにその悪いわけじゃないんですけど、飲み会なのかイベントなのか。例えばボードゲームしましょうみたいなイベントっていうのは、何回かやるとこう。まあ、そういうことじゃない気がするっていう風になってくるわけですよね」(久保氏)
イベントは確かに人を集めるきっかけにはなりますが、それが必ずしも持続的なコミュニティ形成や、当初目指していた「外の人と中の人が交わる」という本質的な価値創造に繋がるとは限りません。
単発的な賑わいを生むだけでなく、人々が継続的に関わりたくなるような「ここに来る理由」をより深く設計していく必要性を感じ始めていたのです。
単なる「作業場所」でもなく、単なる「イベントスペース」でもない。milkが目指すべき独自の価値とは何か? それをどのように創り出し、人々に提供していくのか?
テクノロジーと初期の工夫によって船出したmilkは、次なるステージへと舵を切る必要に迫られていました。それは「場」の運営から、より能動的な「コミュニティデザイン」と「価値創造」への挑戦の始まりでもありました。
次回は、milkがどのようにして地域内外の人々を繋ぐ「ハブ」としての役割を模索し、具体的なアクションを起こしていくのか。その取り組みに迫ります。
【第3回へ続く】▶▷▶
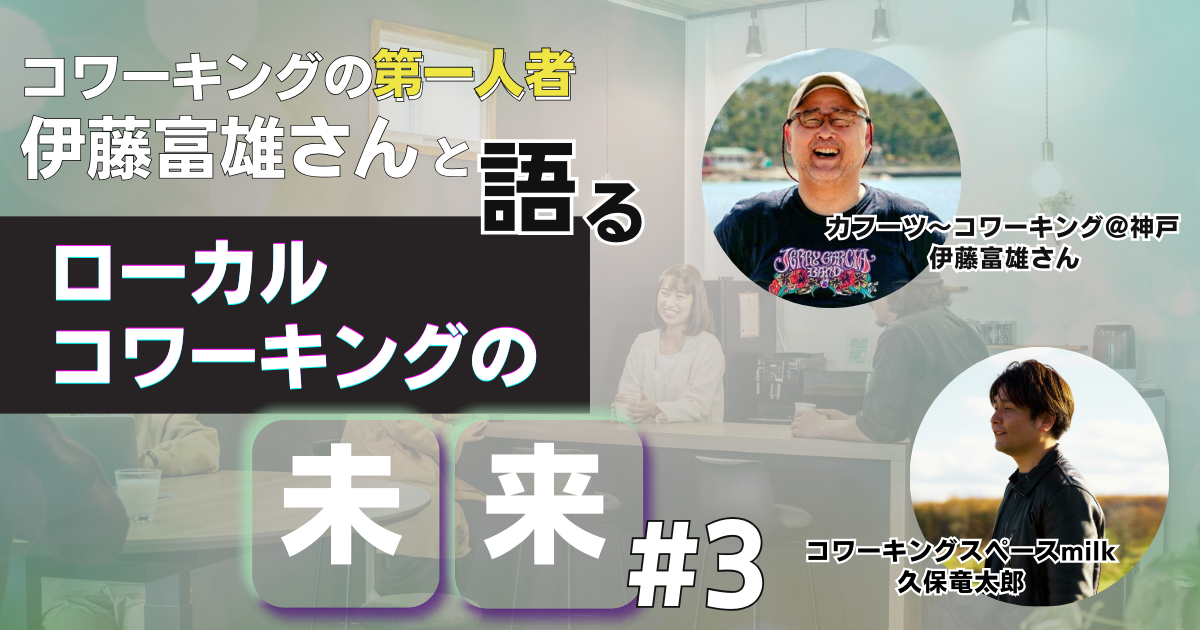
◁◀◁【第1回に戻る】
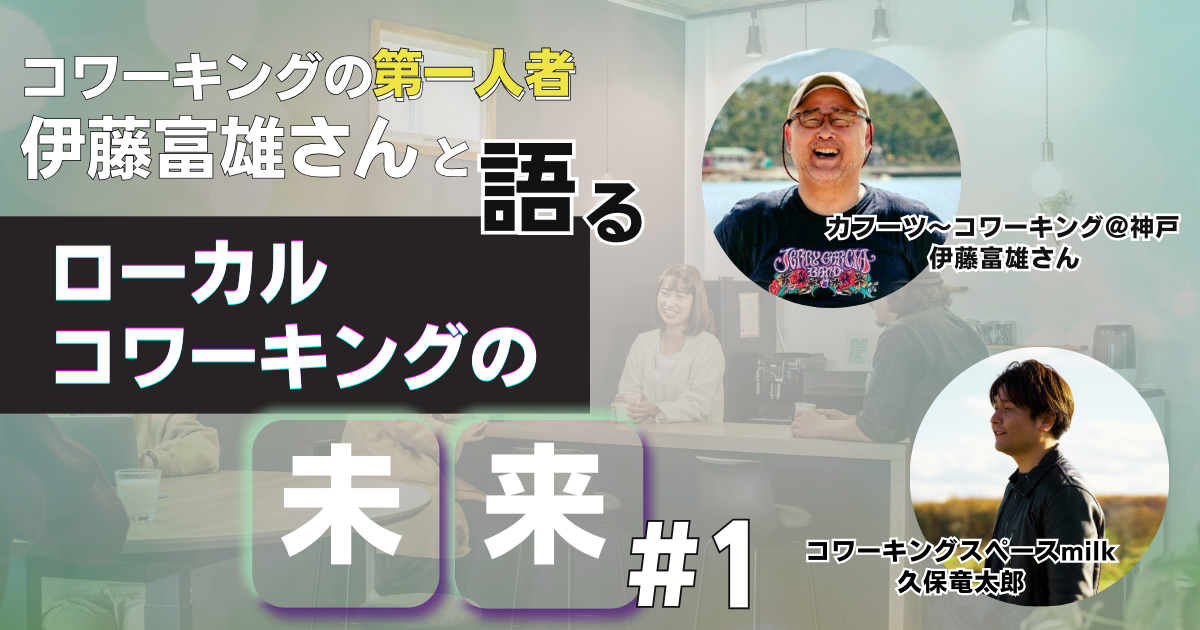
▼対談の全貌はこちらの動画でご覧いただけます!

北海道中標津町を拠点に「最果てを、最先端に」をビジョンとして活動。
コワーキングスペース運営を軸に旅行サービス手配業、まちづくり事業など、地域をフィールドとした様々な実験・プロジェクトを展開しています。

中標津町のコワーキングスペース。
仕事、勉強、打ち合わせ、地域との交流拠点として、どなたでもご利用いただけます。
【営業時間】年中無休 / 6:00〜22:00
【住所】北海道標津郡中標津町東3条北1-6 東龍門2F
カフーツ伊藤さん
日本最初のコワーキング「カフーツ」主宰/経産省認可法人コワーキング協同組合代表理事/コワーキングツアー/コワーキングマネージャー養成講座/Beyond the Coworking〜移働の時代〜 など
また「Beyond the Coworking 〜移働の時代〜」では、2010年に日本初のコワーキングスペースを開設したカフーツ伊藤が、これからのコワーキングとその周辺を軸に、「移働」と「共創」による新しい働き方、新しい生き方、引いては新しい社会についての情報と知見、アイデアを共有しつつ、共に学び、共創し、各自の日々の活動に活かすことを目的としたコミュニティです。