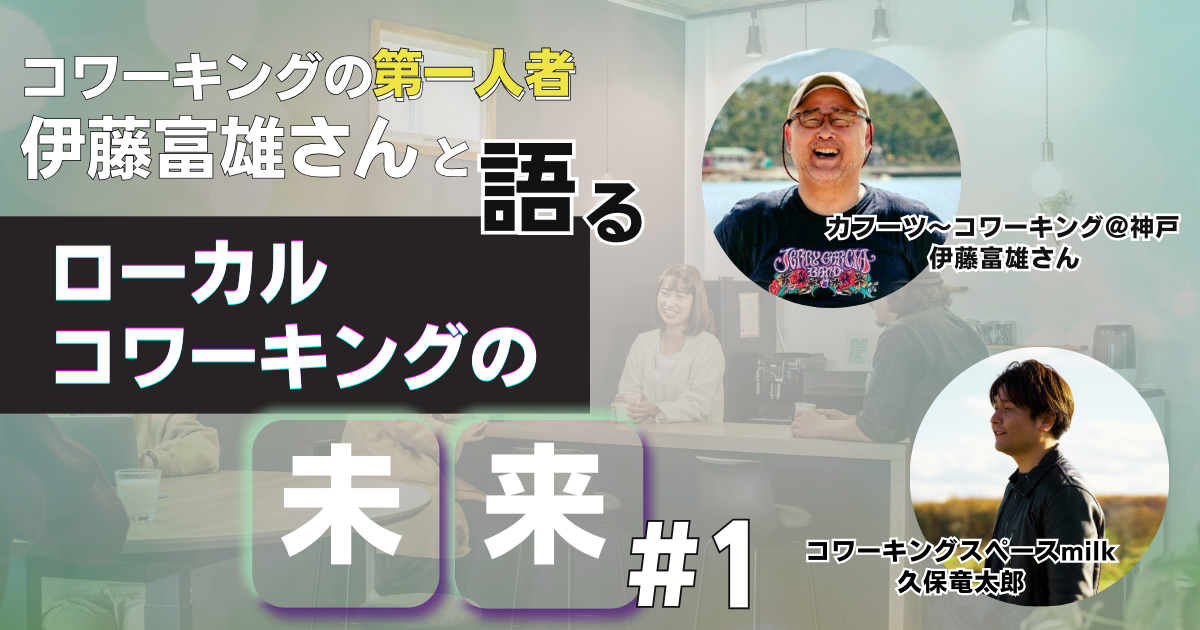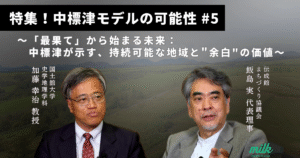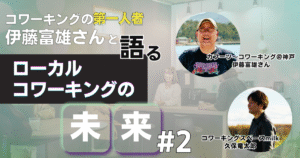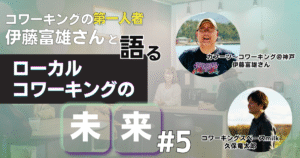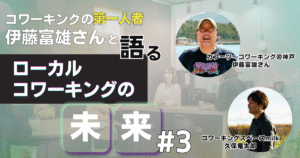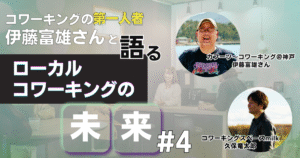第1回:辺境の地に灯った火 – なぜ「コワーキング」は中標津に根を下ろしたのか?
日本各地で地域が抱える課題は深刻さを増しています。
人口減少、少子高齢化、産業の衰退、そしてそれに伴うコミュニティの希薄化や人手不足、縦割りの弊害…。
これらの課題に対し、画一的な処方箋は存在せず、それぞれの地域が独自の活路を見出す必要に迫られています。
そんな中、近年注目を集めているのが「コワーキングスペース」という存在です。
単なる共有オフィスに留まらず、多様な人々が集い、交流し、新たな価値を共創する「場」として、特に地方(ローカル)において、その可能性に期待が寄せられています。都市部とは異なる環境下で、ローカルコワーキングはどのような役割を果たしうるのでしょうか?
この問いを探る上で、貴重な示唆を与えてくれるのが、コワーキングスペースに関する情報発信やコンサルティングの第一人者であり、日本のコワーキング黎明期から業界を牽引してきた伊藤富雄氏が主宰するYouTube番組「トーキング・コワーキング」です。
この番組は、伊藤氏が全国各地のコワーキングスペース運営者を訪ね、その実践知や運営の工夫、地域との関わり方などを深く掘り下げることで、コワーキングという概念そのものの深化と業界全体の発展を目指す、まさに業界の「知の共有地」とも言える場です。
今回、私たちはその「トーキング・コワーキング」Vol.12(2024年3月14日配信 )で取り上げられた北海道東部 道東エリアに位置する標津郡中標津町(なかしべつちょう)の「COWORKING SPACE milk」(以下、milk)運営者、株式会社しるべ代表の久保竜太郎氏との対談を取材しました。
業界の先駆者である伊藤氏との対話は久保氏にとっても自身の取り組みを問い直し、その意義を再確認する貴重な機会となったことでしょう。
この対談からはmilkが単なるワークスペースではなく、地域課題に深く向き合い、新たな可能性を模索する「実験室」としての顔を持つことが浮かび上がってきます。
本シリーズでは全5回にわたり、この対談を手がかりに、ローカルコワーキングが秘める可能性と中標津という地で始まった挑戦の軌跡を追います。
第1回に入る前に、まず問いかけたいと思います。
なぜ、この「辺境」とも言える地に
コワーキングスペースは生まれたのでしょうか?
その答えは運営者である久保氏自身の歩みと、中標津という土地が持つ独特の空気、そして時代の要請の中にありました。
中標津へ:異色の経歴を持つ男の選択
milkの運営者、久保竜太郎氏の歩みは一直線ではありません。
大阪府枚方市で育ち、大学進学を機に北海道北見市へ。大学院で化学を専攻し研究者の道を志すも、実験作業への不向きを自覚し方向転換。分析機器メーカーの営業職に就きます。
しかし、安定したかに見えたキャリアは再び動きます。
「営業職として内定を得た後、より広い世界を知る修行が必要だ」と考え、なんと大学院を中退。ヒッチハイクで日本一周の旅へ。
この型破りな行動力と、未知の世界へ飛び込む探求心こそが、彼の原動力なのかもしれません。
そしてこの旅の過程で、彼は中標津という町と出会うことになります。
彼のユニークな経歴は、後のコワーキングスペース運営における多様な価値観を受け入れる素地となっているのではないでしょうか。
中標津という「ちょうどいい」辺境
久保氏が最終的に根を下ろすことになった中標津町。道東エリアに位置し、周囲を豊かな自然と広大な酪農地帯に囲まれたこの町を、彼は「特殊な町」「ちょうどいい規模感」と表現します。
空港を持ち、町の機能が集約されたコンパクトな構造(「中標津モデル」)を持つ一方で、都市部のような利便性や情報の多さはありません。
久保氏は、この地に秘められたポテンシャルを感じ取っていました。
「なぜこんなところがこんなに知られてないんだ」「もっと(面白い人や活動が)出てきてもいいのに」
しかし同時に、地域内部と外部との交流機会の少なさという、ローカルが抱えがちな課題も認識していたようです。この「ちょうどよさ」と「ポテンシャル」、そして「課題」がmilk設立の土壌となりました。
コロナ禍が生んだ「場」への希求
久保氏が中標津へ移住したのは、ヒッチハイクの旅で縁のできた竹下牧場からの誘いがきっかけでした。当初は竹下牧場の従業員として、ゲストハウス運営や商品開発など様々な新規事業の立ち上げに関わります。
ゲストハウスは元々「外の人と中の人が交わるような仕組み」として作られた場でした。しかしコロナ禍により、不特定多数が交流するゲストハウスのあり方に大きな問いが投げかけられます。
「(コロナ後も)外の人と中の人、初めましての人が交わる空間として宿っていうのはちょっと相性悪いんじゃないか」。同時に、リモートワークの普及により、旅先や地域で仕事をするスタイルが広がりを見せ始めていました。
こうした状況下で「外の人と中の人が交わる、新しい形の場が必要だ」という考えに至ります。その答えとして見出したのが「コワーキングスペース」でした。
特に伊藤氏が提唱するような、単なるワークスペースではなく、多様な人々が集い、繋がり、新たな価値を生み出すコミュニティとしてのコワーキングスペースのあり方に強く共感し、竹下牧場の事業としてmilkの立ち上げと運営に携わることになったのです。
その後、久保氏はこのコワーキングスペース事業に更なる可能性を感じ、「自分の考えで、もっと突き詰めたい」という想いから独立。株式会社しるべを設立し、milkの事業を引き継ぐ形で、新たなスタートを切ることになります。
辺境の地に灯った、小さな火
こうしてCOWORKING SPACE milkは誕生し、そして新たな船出を迎えました。それは久保竜太郎氏という一人の人間のユニークな旅路と、中標津という土地の個性、そして時代の要請が交差した点に灯った、小さな火と言えるでしょう。
それは単なるワークスペースの開業ではなく、地域に新しい風を吹き込み、内にいる人と外から来る人を繋ぎ、ローカルの未来を模索する「実験」の始まりでもありました。
次回は、その「実験室」でどのように人を繋ぎ、「場」をデザインしていったのか。milkの運営における具体的な挑戦と工夫に迫ります。
【第2回へ続く】▶▷▶
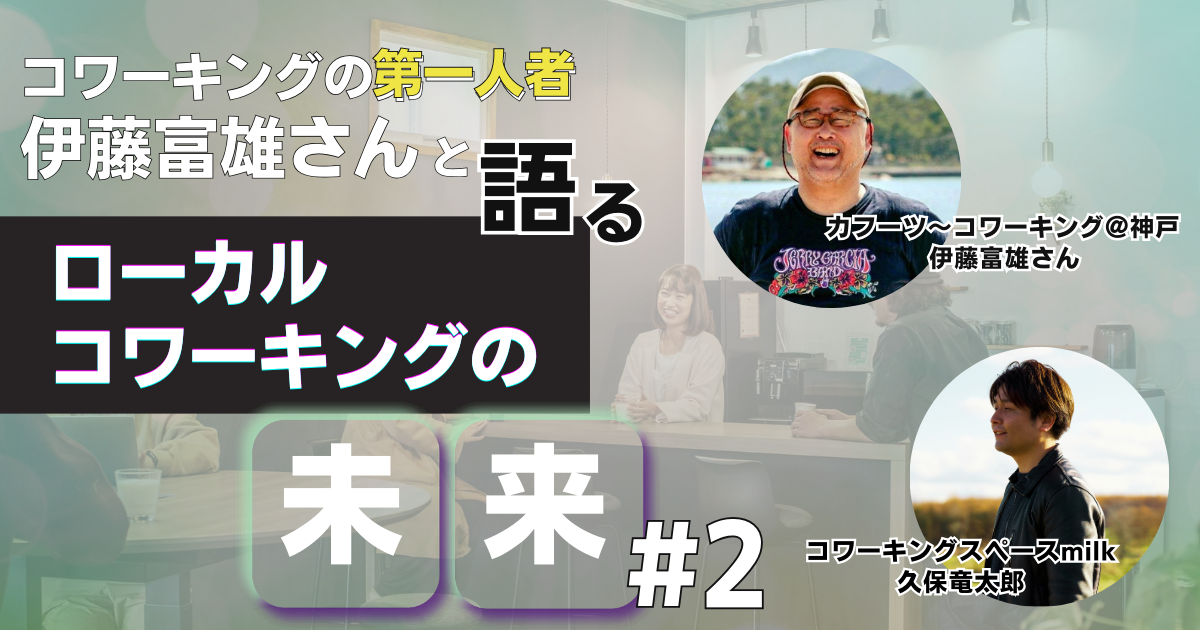
▼対談の全貌はこちらの動画でご覧いただけます!

北海道中標津町を拠点に「最果てを、最先端に」をビジョンとして活動。
コワーキングスペース運営を軸に旅行サービス手配業、まちづくり事業など、地域をフィールドとした様々な実験・プロジェクトを展開しています。

中標津町のコワーキングスペース。
仕事、勉強、打ち合わせ、地域との交流拠点として、どなたでもご利用いただけます。
【営業時間】年中無休 / 6:00〜22:00
【住所】北海道標津郡中標津町東3条北1-6 東龍門2F
カフーツ伊藤さん
日本最初のコワーキング「カフーツ」主宰/経産省認可法人コワーキング協同組合代表理事/コワーキングツアー/コワーキングマネージャー養成講座/Beyond the Coworking〜移働の時代〜 など
また「Beyond the Coworking 〜移働の時代〜」では、2010年に日本初のコワーキングスペースを開設したカフーツ伊藤が、これからのコワーキングとその周辺を軸に、「移働」と「共創」による新しい働き方、新しい生き方、引いては新しい社会についての情報と知見、アイデアを共有しつつ、共に学び、共創し、各自の日々の活動に活かすことを目的としたコミュニティです。