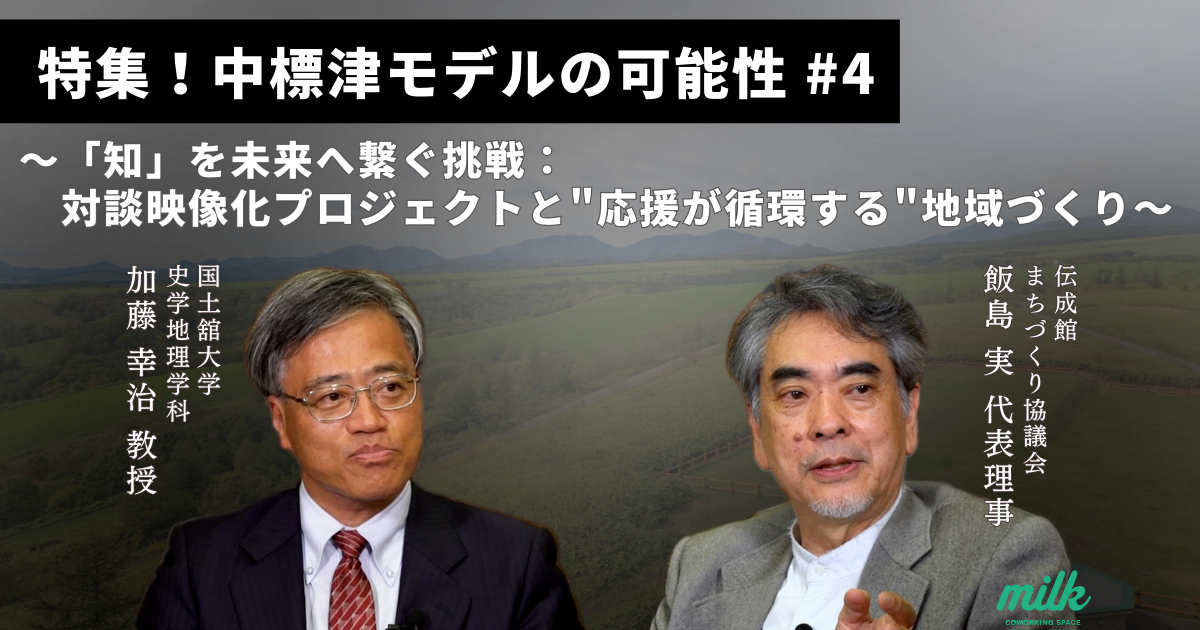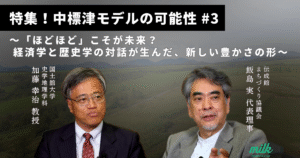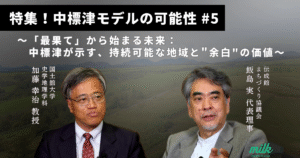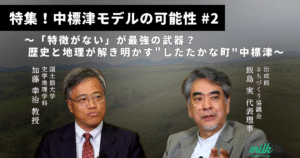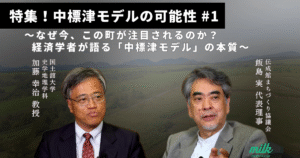専門家によって見出されたユニークな都市構造「中標津モデル」。そして地域の歴史と地理を知り尽くす案内人によって語られた、その奥深い物語。
前3回の特集で紹介してきたように「中標津モデルを経済と歴史で語る会」は、単なる講演会やシンポジウムとは一線を画す、刺激的な知の交差点となりました。
しかし、どれほど価値ある議論が交わされたとしても、それがその場限りのものとして忘れ去られてしまっては、あまりにもったいない。
未来へのヒントが詰まったこの「知」をいかにして記録し、共有し、地域の未来へと繋いでいくか?
本特集第4回はこの対談を単なるイベントで終わらせず、質の高い「映像コンテンツ」としてアーカイブ化するという挑戦に焦点を当てます。
企画者である株式会社しるべ・久保竜太郎氏(コワーキングスペースmilk運営)の視点から、その背景にある想い、資金調達のために選ばれた「クラウドファンディング」という手法、そしてその試みが目指した、地域における「知の循環」と「応援の文化」づくりへの展望を探ります。
なぜ「映像アーカイブ」なのか? 一過性で終わらせない、対談の価値を未来へ
「今回の対談は中標津だけでなく、日本の他の地域にとってもすごく価値のある議論になる可能性がある。この貴重な対談を、ただ開催するだけでなく質の高い映像として記録し、編集して全国の誰でも見られる形でアーカイブしたい!」
このプロジェクトの根底には、対談で交わされた議論の価値を未来永続的な「知的資産」にしたいという強い想いがありました。
「中標津モデル」が示すコンパクトシティのあり方や「ほどほど」「定常型」という新しい豊かさの価値観(特集#1, #3参照)は、インフラ撤退戦や人口減少といった課題に直面する全国の地方自治体や地域づくり関係者にとって、重要な示唆を与える可能性があります。
また飯島氏が語った中標津のユニークな歴史や地理(特集#2参照)は、地域資源の掘り起こしやその土地ならではの魅力発信のヒントにもなり得ます。
これらの内容を、時間や場所の制約なく誰もがアクセスできる「映像」という形で残すこと。
そして単なる記録ではなく、編集によって論点を分かりやすく整理し、繰り返し参照され、議論を呼び、新たなアクションを生み出す「きっかけ」となるようなコンテンツにすること。
それが、映像アーカイブ化を目指した理由でした。
なぜ「クラウドファンディング」だったのか? 資金調達以上の意味を持つ挑戦
しかし、質の高い映像制作には、撮影機材や専門スタッフ(編集者など)の費用がかかります。そこで選択されたのがクラウドファンディングによる資金調達でした。
ですが、その理由は単に「予算がないから」だけではなかった、と久保氏は言います。
「この『クラウドファンディング』という手法自体に、ぼくがこの地域で実現したい、もう一つの大切な想いが込められています。それは『地域の中で、新しいチャレンジが生まれ、応援される文化を作りたい』ということなんです」
【地域課題解決とクラウドファンディングの可能性】
地方では「これは絶対に価値がある!」と思うアイデアがあっても、「お金がないから」という理由で実現を諦めてしまうケースが少なくありません。クラウドファンディングはそうした状況を打破する可能性を秘めています。
行政の予算や補助金だけに頼るのではなく、プロジェクトの価値に共感した地域住民や関係者、あるいは地域外のファンからの「応援」によって資金を集める。
これは単なる資金調達ではなく、プロジェクトの価値を社会に問い、多くの人を巻き込み、当事者意識を醸成していくプロセスそのものと言えます。
近年、全国の地域活性化プロジェクトでクラウドファンディングが活用されている背景には、こうした意義への期待があります。
【「チャレンジを応援する文化」と「ハブ」の役割】
久保氏はさらに、クラウドファンディングを通じて「失敗してもいいから、まずはやってみよう!」というチャレンジを、地域全体で応援し合える文化を中標津に根付かせたい、と考えていました。
そして、そのための「ハブ」として、コワーキングスペースmilkが機能することを目指していました。
「個人でクラファンを立ち上げるのって、結構大変。だから、milkみたいな場所が『何かやりたい!』って人の相談に乗って、一緒に企画を練って、クラファン立ち上げをサポートする。失敗してもいい。でも気軽にチャレンジできる土壌、そしてもし失敗しても次に繋げられる文化を、この場所から作りたい」
今回の対談映像化クラファンは、まさにその「ハブ機能」の試金石であり、自らリスクを取って「言い出しっぺ」になるという、久保氏自身の覚悟の表れでもありました。
クラウドファンディングの結果と、そこから見えたもの
結果として、このクラウドファンディングは、目標金額15万円に対し、26名から18万3000円もの支援を集め、無事目標を達成しました。
この結果は対談企画そのものへの期待の高さを示すと同時に、地域内外からの「共感」が具体的なプロジェクトを後押しする大きな力になることを証明しました。
そして「チャレンジを応援する文化」づくりに向けた、小さな、しかし確かな一歩となったと言えるでしょう。
専門家の深い「知」と、地域に眠る「物語」。そして、それらを未来へ繋ごうとする人々の「挑戦」と、それを支える「共感」。
これらが結実して生まれた「中標津モデル」対談の映像は、現在YouTubeで公開されじわじわと再生回数を増やしています。
最終回となる次回【特集#5】では、この対談から得られた学びを踏まえ、中標津、そして日本の地方がこれから描くべき未来像について改めて展望します。
(特集 第5回へつづく)▶▷▶
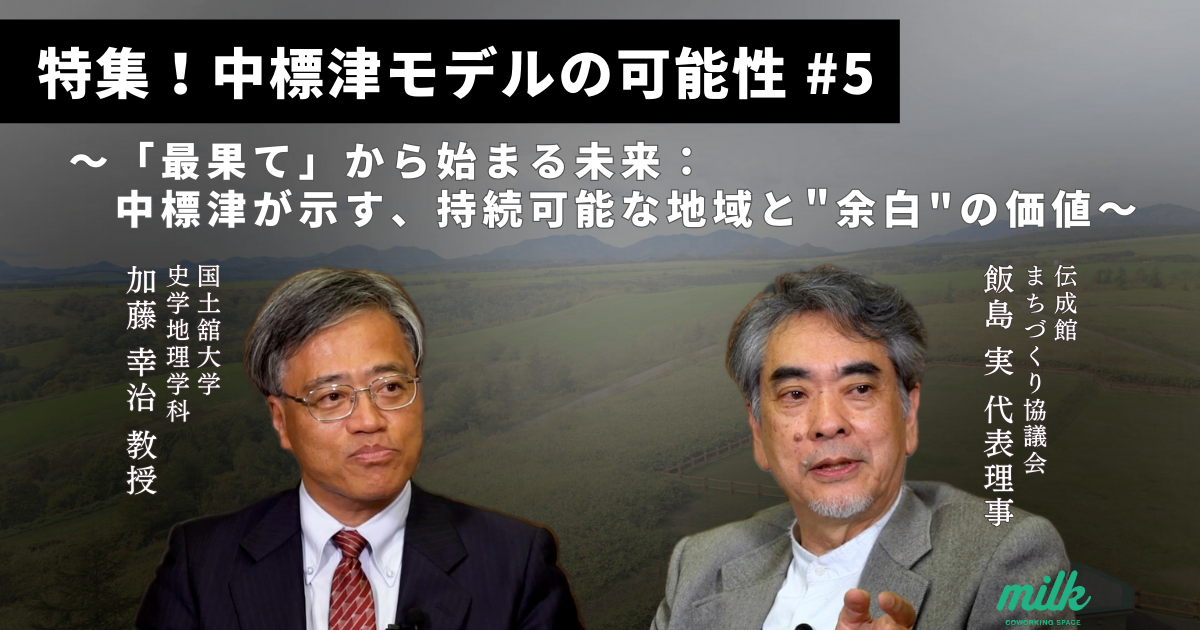
◁◀◁(特集 第3回に戻る)
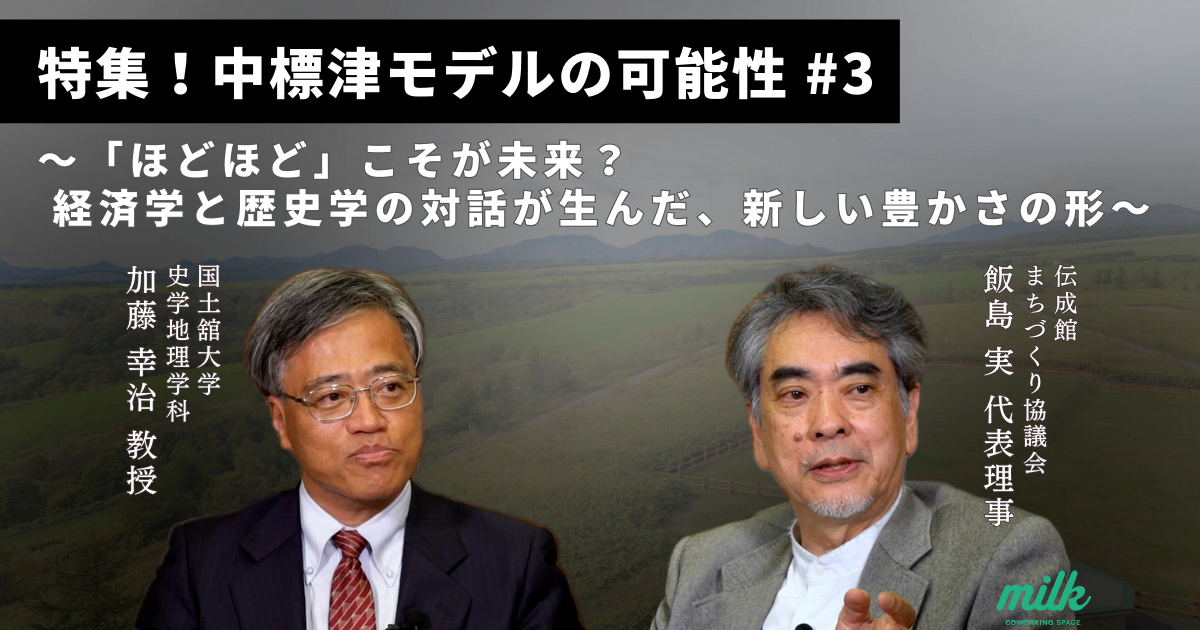
本記事は、2022年9月9日に北海道中標津町の「伝成館」にて行われた、国士舘大学 加藤幸治教授とNPO法人伝成館 飯島実理事長による対談「中標津モデルを経済と歴史で語る会」(主催:コワーキングスペースmilk / 株式会社しるべ)の内容に基づき構成しています。対談の記録映像制作にあたっては、クラウドファンディングを通じて全国26名の方々から18万3千円のご支援をいただきました。心より感謝申し上げます。
▼対談の全貌はこちらの動画でご覧いただけます!

北海道中標津町を拠点に「最果てを、最先端に」をビジョンとして活動。
コワーキングスペース運営を軸に旅行サービス手配業、まちづくり事業など、地域をフィールドとした様々な実験・プロジェクトを展開しています。

中標津町のコワーキングスペース。
仕事、勉強、打ち合わせ、地域との交流拠点として、どなたでもご利用いただけます。
【営業時間】年中無休 / 6:00〜22:00
【住所】北海道標津郡中標津町東3条北1-6 東龍門2F