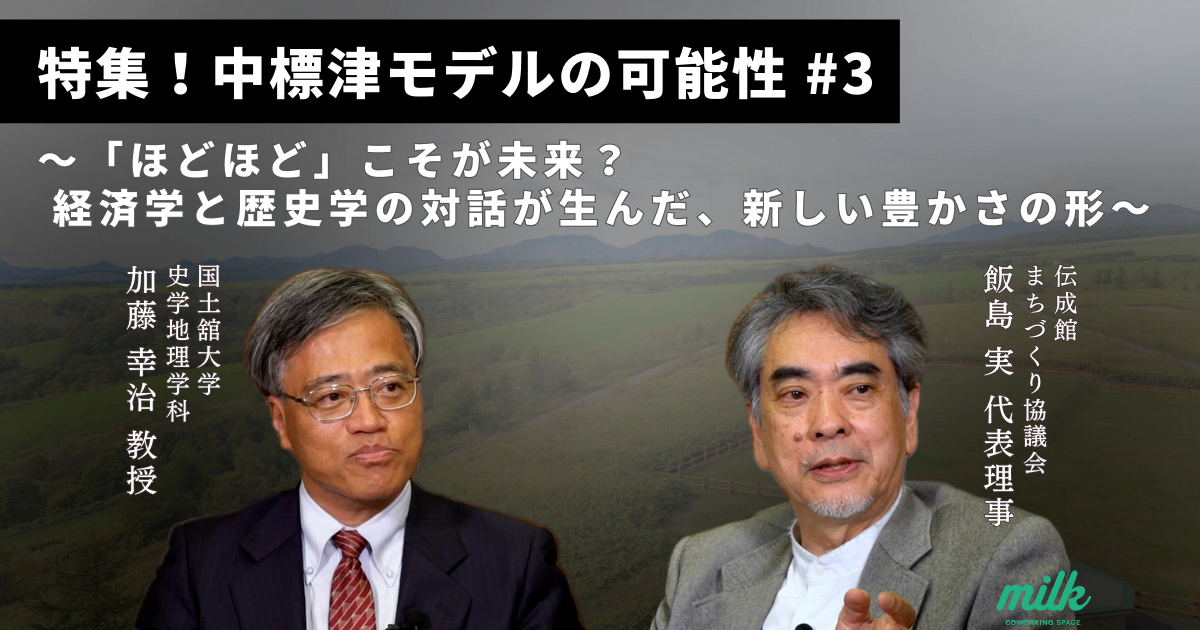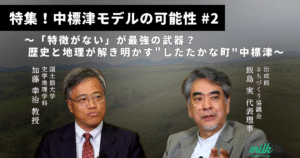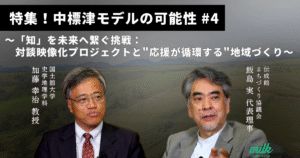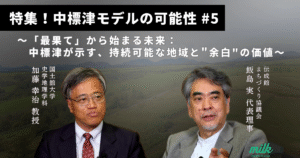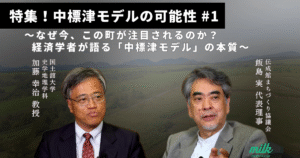経済学的な合理性から見出された「コンパクトシティ」としての側面(特集#1)。
そして、歴史と地理の文脈から浮かび上がる「特徴がないこと」「余白があること」の独自の価値(特集#2)。
北海道東部の町、中標津が持つこの二つの顔は一見すると相反するように見えるかもしれません。
しかし、国士舘大学の加藤浩嗣教授(経済地理学)とNPO法人伝成館の飯島実理事長(中標津の歴史・地理)による異色の対談はまさにこの異なる視点がぶつかり合い、化学反応を起こすところに、その真髄がありました。
本特集第3回は「中標津モデルを経済と歴史で語る会」の中で繰り広げられた、スリリングな知の応酬を追体験します。
計画と偶発性、中心と周縁、成長と定常…。
対立するように見える概念が中標津というユニークなフィールドを通じてどのように繋がり、これからの地域づくりにおける「新しい豊かさ」の可能性を示唆したのか、探っていきましょう。
対話①:「偶然」のモデルか、「必然」の設計か? 成り立ちをめぐる視点の交錯
加藤教授は、中標津のコンパクトな都市構造を「偶然の要素が強い」と分析しました
しかし飯島氏は地域の歴史を紐解きながら、そこに単なる偶然ではない「必然性」や「計画性」の痕跡をいくつも見出していきます。
「(中標津の地名の由来について)標(しるべ)という文字が標準の標だって言ってる人はまだまだ浅い」「松浦武四郎の時代、もっと古い文明文化、非常に造詣の深い人がこの文字を選んだ理由…」
「(開拓の拠点・伝成館ができた場所は)武佐岳のフタコブが一つに重なる場所。最高の目印になりうる場所」
「(防風林は)入植した人たちの区画を守るために、非常に細かい配慮をしながら配置されている」…。
飯島氏が語る、地名に込められた深い意味、地形を利用した目印、緻密に計画された防風林の配置、さらにはリンドバーグやスターリンといった歴史上の人物がこの地に関心を寄せていた(かもしれない)というエピソードは、中標津という土地が持つ単なる経済合理性では説明できない、歴史的・地理的な重要性を示唆します。
経済学的な「モデル」としての分析と、歴史・地理に根差した「物語」としての解釈。この二つの視点が交錯することで、中標津モデルの成り立ちがより立体的で多層的なものとして浮かび上がってきます。
それは、トップダウンの計画と現場の知恵や自然条件、そして歴史の偶然が複雑に絡み合って生まれた他に類を見ない「作品」と言えるのかもしれません。
対話②:「商業の中心」か、「何もない原っぱ」か? 地域の“核”をめぐる多様な解釈
対談では「中標津の中心とは何か?」という点も興味深い論点となりました。
加藤教授は東武サウスヒルズのような地元資本の大型商業施設が広域から人を集め、地域経済を循環させる「商業の中心地」としての機能、そして地域の人々が主体となった「内発的発展」の重要性を強調します。
それに対し飯島氏は「この町には、中心地らしき地名はいろいろあるけれど、点々と移ってきた」「今の中心は、昔の駅の跡地…つまり『何もない原っぱ』だ」と、ユニークな視点を提示します。
「夏祭り、冬祭りには、いろんな地域からその原っぱに人が集まる。何もないところにみんなが集まるところに、この町の役割がある。(中略)何もない草一面の贅沢な原っぱ、何やってもいいよなんて言われる。そんな原っぱがあること自体が、本当に夢のような世界。それこそが中心としての重要な価値がある。」
この対話は「地域の核」とは、必ずしも物理的な施設や中心市街地だけを指すのではないことを示唆しています。
人々が集い、交流し、多様な活動が生まれる「場」そのもの、あるいは何にでも使える「余白」や「可能性」こそが、地域の真の中心となり得るのかもしれません。
対話③:奇跡の収束点 – 「ほどほど」と「定常型社会」という未来の豊かさ
経済と歴史、それぞれの視点から中標津を分析してきた対談は、終盤、驚くべき収束を迎えます。
それは「中標津は無理に成長や拡大を目指すのではなく、この“ほどほど”の規模感を保ち、その豊かさを享受していくのが良いのではないか」という、共通の認識でした。
加藤教授は経済学の視点から「定常経済(Sustainable Economy)」という概念に触れます。
「やたら成長成長とか拡大とかっていうんじゃなくて、定常できるっていうのが、まあ経済学なんかでも言われてる。まさにそんな感じでいくといいんじゃないですか」
「(中標津は)成長していくっていうけど、それってそもそも無理がありませんか、みたいなことに(もともと)バッチシあっているのかなっていう」無理な成長を追い求めることから解放された、持続可能な経済社会のあり方です。
一方、飯島氏は中標津の厳しい自然環境(寒さ、雪)こそが、過度な開発や人口集中を抑制し、結果的に「ほどほど」の良好な状態を保つ要因になったのではないか、と指摘します。
「良すぎるとね、とかく良くないことが起こっちゃう。ここの厳しさがあるおかげでね、ほどほどのところにこの地域が収まっていると思う」。
そして防風林がもたらす「日陰」や、広大な土地が生む「余白」が、目に見えない「安心感」や「豊かさ」に繋がっていることを示唆します。
経済成長が必ずしも幸福に直結しないことが明らかになりつつある現代。
「GDP(国内総生産)」のような経済指標だけでは測れない、新しい「豊かさ」の物差しが求められています。
それは自然との共生、地域コミュニティの繋がり、文化的な深み、時間的なゆとり、そして未来への持続可能性といった要素かもしれません。
中標津が(意図せずとも?)体現しているかもしれない「ほどほどの豊かさ」「定常型の暮らし」は、まさにこれからの脱成長時代・成熟社会における、一つの理想的な地域のあり方を示しているのではないでしょうか。
経済と歴史、計画と偶発性、中心と周縁、成長と定常…。
一見、対立するように見えるこれらの概念が中標津というユニークなフィールドを通じて見事に響き合い、新しい価値観を提示した今回の対談。
しかし、この対談で生まれた貴重な「知」を単なる記録として終わらせず、どのように未来の地域づくりへと繋いでいくことができるのでしょうか?
次回【特集#4】では、この対談を企画・実現したプロセスと、その記録を未来への「資産」とするための挑戦に焦点を当てていきます。
(特集 第4回へつづく)▶▷▶
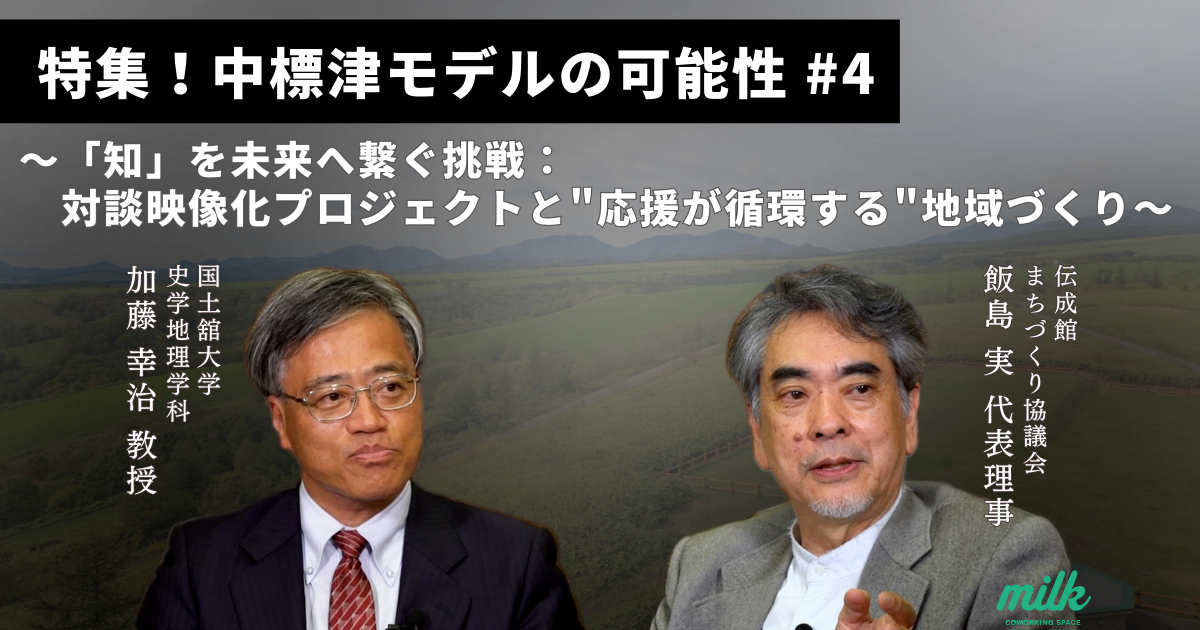
◁◀◁(特集 第2回に戻る)
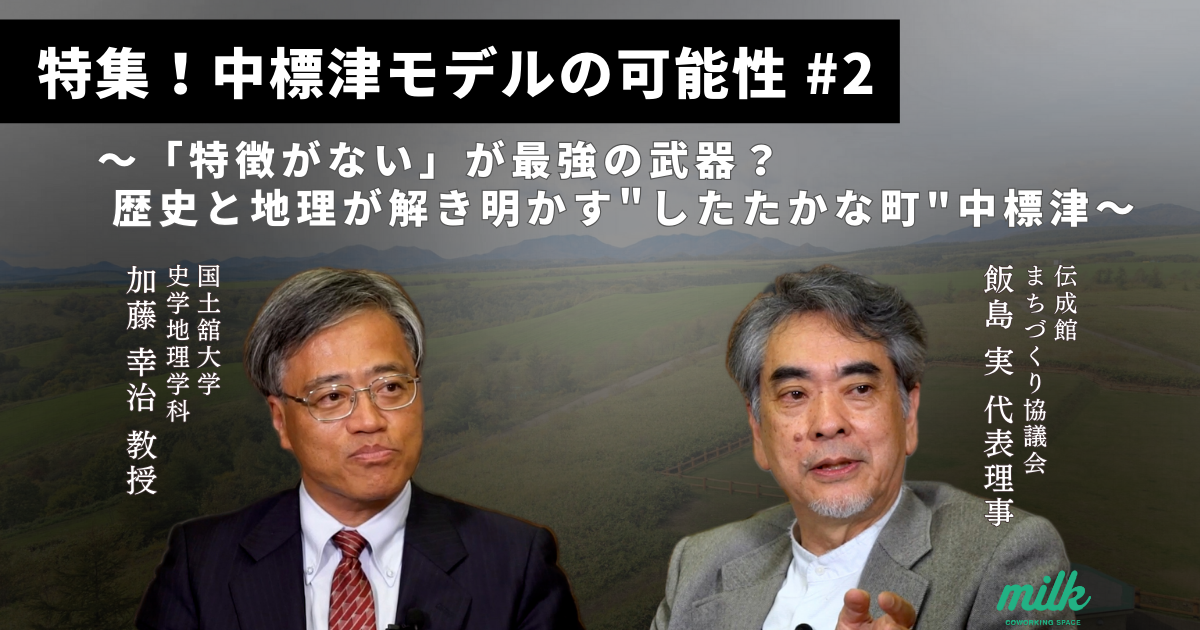
本記事は、2022年9月9日に北海道中標津町の「伝成館」にて行われた、国士舘大学 加藤幸治教授とNPO法人伝成館 飯島実理事長による対談「中標津モデルを経済と歴史で語る会」(主催:コワーキングスペースmilk / 株式会社しるべ)の内容に基づき構成しています。対談の記録映像制作にあたっては、クラウドファンディングを通じて全国26名の方々から18万3千円のご支援をいただきました。心より感謝申し上げます。
▼対談の全貌はこちらの動画でご覧いただけます!

北海道中標津町を拠点に「最果てを、最先端に」をビジョンとして活動。
コワーキングスペース運営を軸に旅行サービス手配業、まちづくり事業など、地域をフィールドとした様々な実験・プロジェクトを展開しています。

中標津町のコワーキングスペース。
仕事、勉強、打ち合わせ、地域との交流拠点として、どなたでもご利用いただけます。
【営業時間】年中無休 / 6:00〜22:00
【住所】北海道標津郡中標津町東3条北1-6 東龍門2F